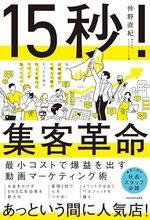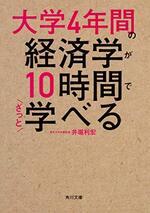町の本屋はどのようにして競争に破れてきたのか
中小書店は1960年代から赤字だった

かつて「ふらっと立ち寄る」「雑誌の発売日に必ず行く」場所だった本屋は、いまでは「本好きが、わざわざ行く」場所になっている。新品の書籍・雑誌を扱う、地元資本の「町の本屋」の商売はどのように成立し、どのような背景から競争に敗れ、つぶれてきたのだろうか。
日本の紙の出版市場は1990年代半ばをピークに減少傾向がつづいている。マンガ喫茶や新古書店、図書館の増加、ネットやスマホの普及など、さまざまなものがその「犯人探し」の標的になってきた。しかし、出版市場が最盛期に向かおうとする1980年代後半からすでに、町の本屋は年間千店舗単位でつぶれはじめている。
じつは、1960年代後半の調査で、平均的な中小書店はすでに赤字だった。小売業ワーストクラスの利益率の、本の値段が安く、経営が成り立っていなかったのだ。また、ネットやスマホの登場以後も、米濠仏伊独などの国では紙の本の市場はくずれていない。なぜ日本ではそうならなかったのだろうか。
その一因に、出版-取次-書店の「垂直的な取引関係」がある。取次と出版社によって書店業のマージンやキャッシュフローは決められてしまうが、それは町の本屋にとっては厳しい条件だ。そのため、経営を成り立たせるためには、書籍や雑誌以外の「兼業商品」を扱ったり、書店側から客先へ出かける「外商」が必要となった。
本を売る店同士の「小売間競争」もある。本屋以外にも、本や雑誌を扱うさまざまな店舗や図書館流通センターなどとも争わなければならないのだ。「垂直的な取引関係」によって構成される書店業界の課題は長年変わっていないが、周辺の動きはどんどん移り変わっている。町の本屋がつぶれてきたのは、書店業をめぐる諸問題の根源を先送りにしてきた結果だ。
【必読ポイント!】 書店に不利な、新刊書店のビジネスモデル
本は安いし、本屋の取り分が少ない
新刊書店は、小売側に価格の決定権がほとんどない。出版社、本の卸売・流通を担う取次、書店の三者の間で「再販売価格維持契約」が結ばれ、出版社が本の値付けをし、本屋は読者に定価で売ることを約束させられている。現在では、小売店に自由に価格を決めさせない契約のほとんどは違法だが、本屋には売れない在庫の安売りをすることも、品薄の本を高く売ることも許されていないのだ。