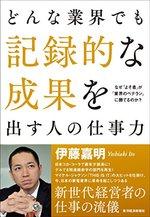考え方を変える
質問に対する考え方を変える
質問術に秀でるためには、脳内の配線を少し変える必要がある。質問とは発見であり先入観のない好奇心の表現である、と捉えなおすことがもっとも重要な変更点だ。問い詰めたり詮索したりすることは相手を不快にさせるだけではないかと質問をためらう人がいるが、本来なら質問は相手への関心を示す手段なのだ。
質問の出し方次第では、聞かれた本人も自覚していない有益な情報を引き出すことも可能だ。例えば、事故や犯罪の現場付近で適切な聞き込みを行うことで、自分は何も知らないと思っていた通行人さえもときに重要な目撃者となる。誰でも適切な質問をされれば、役に立つ情報の提供者になれる。質問の腕を磨くためには、「発見」に焦点を置くことを忘れてはならない。
2歳児の疑問文/「他には?」

訓練経験のない者が自発的に質問した場合、無関係な情報や有益ではない情報が答えに入ってきてしまうことも多い。
上手な質問をするための初歩的な練習は、2歳児に戻ったつもりで相手に質問をすることだ。知らない話題について「だれ」「何」「いつ」「どこ」「なぜ」を含む簡単な疑問文で、一度に一つずつたずねながら理解を深めていく。
加えて重要なことは、一つの情報を掘り下げる前に「他には?」とたずね、すべての情報が出尽くすまでこれを繰り返すことだ。相手が「他にはありません」と答えるまで聞けば、これ以上聞きだせる情報はない。それを確認してから新たな質問に移る。
質問を「発見」と考えること、答えが「はい」「いいえ」ではなく文章になる質問を一度に一つ心がけること、そして「他には?」と聞くこと、まずはそのように意志をもって行うことが重要である。
上手な質問の作り方
質問は正確さと効率が決め手

質問上手になる鍵は、いつも疑問詞を使って短く聞くことだ。