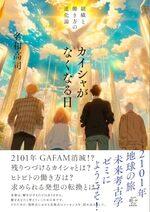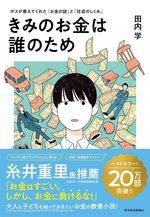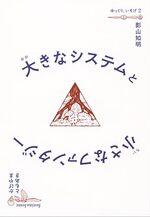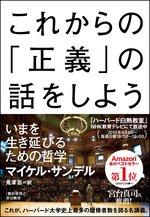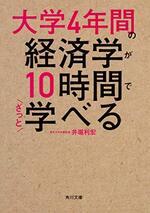【必読ポイント!】 人間の調整能力を発揮するための仕組み
「市場」と「企業」

火の使用、車輪の発明、蒸気機関の開発など、人類はこれまでさまざまな発明をしてきた。しかし人類史を貫く一本の重要な糸として、人間のもつ調整能力を忘れてはならない。人間は調整能力を活かして、ピラミッドなどの大規模な建造物を設計・建設してきたし、古代のアレクサンドリア図書館や現代のウィキペディアのように、膨大な知識を共同で収集してきた。月面着陸も膨大な数の人の力を調整して、なし得た偉業である。
現代において世界人口の衣・食・住、教育、雇用を支えられているのは、「市場」と「企業」という2つのソーシャル・イノベーションのおかげだ。どちらも効率的な調整の支援を目的としているが、市場は分権化されているのに対して、企業は集中管理型の構造をしている。両者は相互に補完し合う関係ではあるが、激しく火花を散らし合う存在でもある。市場では誰もが情報を発信し、受け手になることで、参加者全員が分権的に意思決定を行う。一方で階層型の企業では、中心へ情報が流れていき、リーダーが重要な意思決定を下す。
これまでは、そのときどきで市場が競争優位に立ったり、企業が競争優位に立ったりしてきた。しかし来るべきデータ時代には、市場が大きく進化し、市場と企業の長年の戦いに新たな章が開かれることとなるだろう。
貨幣と価格が果たした情報伝達の機能
「市場における情報は多いほうがいい」という意見が大勢を占めている。だが現実には完全な情報が共有されることはなく、私たちはいつも不完全で非対称な情報にもとづいて選択しなければならない。一方で情報が多すぎると、処理しきれずに選択を誤ってしまう可能性もある。必要な情報を安価で高速にやり取りできたとしても、私たちの認知能力には制約があり、合理的とは思えない選択をしてしまうこともある。
「貨幣」はこういった問題を和らげる存在だ。貨幣は希少な貴金属を鋳造することで、価値を蓄積・保存する。だがそれ以上に重要なのが、価格により市場を機能させ、製品やサービスの価値を表現するための尺度としての役割だ。貨幣が存在せず、市場で物々交換をしていた時代には、それぞれの品物がどれくらいの品物と釣り合いがとれるのか、合意を取るのはとても面倒な作業だった。だが共通の尺度としての貨幣と価格の存在は、市場参加者全員が理解可能な共通言語で、取引情報を表現できるようにした。貨幣中心市場が到来したことにより、情報の流通量が妥当な水準に抑えられ、人間は市場の調整機能の可能性を引き出せるようになった。
貨幣と価格の呪縛からの解放

とはいえ現代における情報の伝達・処理能力の向上は著しい。もはや価格というたったひとつの数字に、あらゆる情報を凝縮するのは正しいあり方とは言えない。多様な情報を価格だけに凝縮していく過程で、多くの詳細が抜け落ちてしまうからだ。たとえばある商品を購入する際は、商品の良し悪しや買い手の好み、いますぐ欲しいかどうかなどの細かい要素が入り混じって、「買ってもよい」と思える価格が形成される。しかし売り手にできるのは、ひとつひとつの条件を考慮することなく、売上や在庫を考えながら価格を提示することくらいである。これでは買い手と売り手の思惑を事細かな情報として価格に込めたり、伝達したりすることはできない。私たちが価格に固執すれば、市場は本来の機能である調整力を発揮できなくなってしまう。
この問題の解決策は、デジタル決済や仮想通貨の開発・導入のように、貨幣をあれこれいじり回すことではない。