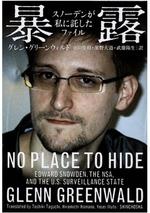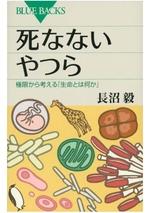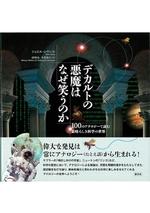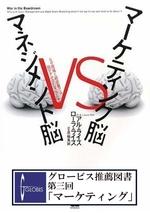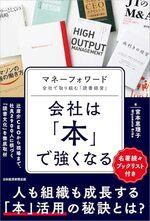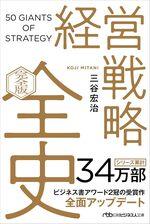サブプライムショック後のトヨタ減収収益
販売不振は予測できなかったのか
リーマン・ブラザーズの破綻に象徴されるサブプライムショックが起こり、実業の世界をも恐慌が襲った。それまで日本企業で一番優良企業だったトヨタ自動車はたいへんな打撃を受けた。
トヨタの売上減少額は5.8兆円、営業利益の減少額は2.7兆円にものぼった。自動車業界は、他の製造業に比べ、おしなべて販売成績が対前年で落ち込んだが、なかでもトヨタの減収収益はとびぬけて大きかった。
一番大きな要因は、北米の自動車販売数の大幅な減少だ。北米市場の自動車販売数は、トヨタも、市場全体も、対前年で30パーセント台の減少率にまで落ち込んだ。売上が3分の1減るということは、大企業の経営ではほとんどありえない。
自動車が最優先で切り詰められる――短期所得弾力性

この、自動車業界全体を襲った激震は、著者によると経済学の理論をもとにすれば予測できたのだという。経済が高度にグローバル化している現在こそ、経営者は、マクロ経済のレベルで起きることに対処する能力を持たなければいけない。
リーマンショック後、アメリカの経済成長率はマイナス6%成長になった。つまり、アメリカ人ひとりのレベルでいえば、年収が6%減ったことになる。すると生活はどうなるか。支出が切り詰められることになる。
支出が切り詰められるとき、切り詰められやすい商品とそうでない商品がある。これは「短期所得弾力性」という数字に表されている。
短期所得弾力性というのは、もし所得が1%減ったら、その商品を買うのに使うお金がどれだけ減るかという数字だ。たとえば、外食の短期所得弾力性は1.6だ。これは所得が1%減ると外食に使うお金は1×1.6=1.6%減ることを意味する。
自動車の短期価格弾力性は、5.5%。つまり、年収がマイナス6%であるということは、需要がその6×5.5=33%というものすごいレベルで激減するということだ。
この数字は、このたびの北米自動車市場の減少率にぴたりと重なる。試しに、アメリカの経済成長率に5.5をかけたグラフと、北米市場の自動車販売数増減率のグラフを重ねると、ほぼ一致するのだ。
需要は急回復する――長期価格弾力性

さらに経済学の知識を使ってみよう。短期所得弾力性に対して、長期所得弾力性という数字がある。
一時的に所得が減ってしまうときの行動が「短期」の行動なのだが、時間がたってそれに慣れてきたときにとる行動は「長期」の行動という。これからずっと収入が低いままだとわかったとき、人間は、1年もすると「長期」の所得弾力性に合わせた行動をとりはじめる。