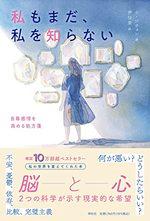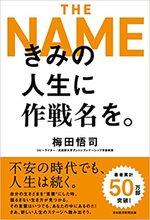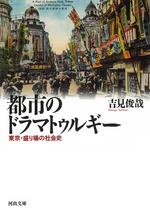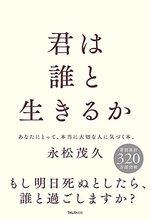4畳半で繰り返し読んだ、少年漫画
「大人は信用できない」はどこから来たのか
そもそも最初に読んだ本はなんだったかと考えると、漫画だったのではないかと鈴木さんは振り返る。漫画好きの親父が初めて買ってくれたのは月刊少年漫画誌『少年画報』。なかでも夢中になったのは『赤胴鈴之助』だ。錚々たる剣士が集う、江戸の千葉周作道場で、少年剣士・赤胴鈴之助の活躍が描かれる。
『赤胴鈴之助』が大人気だったのは、子どもたちの間にあった「大人は信用できない」という気分にあったように思う。戦時中は戦意高揚の道具として使われた小説・漫画・映画は、戦後の一時期禁止された。独立とともにもう一度解禁されたとき生まれたのが『赤胴鈴之助』だ。この時期子どものための漫画が生まれたのは、戦後しばらくは戦争孤児がたくさんいて、貧困でつらい目に遭っていたからかもしれない。それは日本が戦争に負けたせいで、その戦争をやっていた大人は信用できないという気分が時代の根底にあった。だから、戦後の漫画は子どもが主人公になり、悪い大人と戦うものが多い。鈴木さんの知るかぎり、こういう物語は日本に特有の現象だ。
戦後のヒーローを生み出したのは、食うために漫画を描いた、16、17歳ぐらいでデビューした漫画家たちだ。医学部卒の手塚治虫という例外はいるが、日本の漫画界の根っこには、戦後の貧しさや学校に行けなかった人たちがいる。主人公が少年だったのは、作家自身が一家を支えるために必死で闘っていた現実とリンクしている。
日本独自の文化が、世界へ羽ばたくまで

戦争孤児よりも下の世代である鈴木さんの時代にも、まだ貧しさは残っていた。漫画や本が潤沢にあった自分は恵まれていたのだろうと振り返る。4畳半の部屋に漫画をたくさん置いて、繰り返し読んでいた。
義務教育を終えると同時に漫画家になる人たちがたくさんいて、そういう漫画を浴びるように読んだ最初の世代が、鈴木さんたち団塊の世代だ。この世代は、漫画を「卒業」せずに、大人になっても漫画を読み続けた第一世代でもある。
戦争が終わり、アメリカに占領され、大人が自信を失っていた時期に、子どもが社会の主役として躍り出て、日本独自の子ども文化が誕生する。それは、文化的にも商売的にも画期的だったのではないかというのが鈴木さんの見立てだ。
「自分が主役にならなきゃいけない」という意識は漫画によって植え付けられた。立派な大人ではなく、立派な少年になってこの国をなんとかしなければならないと思ったのだ。宮さん(宮崎駿)が、少年が旅立ち、苦難を経験し、成長するという物語をつくりたがったのも、あの時代の漫画を読んでいたからだ。