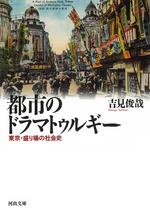〈自分〉と〈他人〉——みんな仲良しというタテマエ
「みんな仲良し」の「みんな」はどこへ行ったのか
「みんな仲良し」といわれたとき、多くの人は「タテマエだ」と感じることだろう。著者が子どもの頃、学校で習った「みんな仲良し」はあらゆる場所で通用した。学校でも近所でも、「みんなおたがいさま」で丸く収まっていたのだ。
昔はとなり近所であればおたがいのことをよく知っていたが、いまでは同じマンションに住んでいる人の顔すら知らないことがほとんどだ。昔は「みんな」という言葉が誰から誰までを指しているのかイメージができたが、いまは「みんな」の顔が見えにくくなっている。だから、昔と同じように「みんな仲良く」と言われるとタテマエに聞こえてしまう。
「日本人」も「みんな」ではなくなった。海外との行き来が盛んになったいまでは、どんな国や民族、文化でも、人の出入りがある。所属している場にいる人がそのまま「みんな」になる時代は終わったのだ。
幸せに生きるための2つの条件

社会学者は、人が幸せに生きるためには2つの条件が必要だと考えてきた。
1つめの条件は「自由」であること。選択肢を知って、それを選べることだ。もっと言えば、「選ぶ能力」があることも重要だ。選択肢を知っていても選ぶ力がなければ、つらい環境に身を置いたとき、安易に「他者のせい」にしたり「自分のせい」にしたりしかねない。
幸せに生きるための条件を「尊厳(自尊心・自己価値)」という観点からも考えてみよう。どんな社会にも文化があって、どんな人が自由に生きやすいかがある程度決まっている。「自由」があるだけでは、多数派や強い人たちの色に社会が染まりすぎてしまう。みんなが「尊厳」をいだいて生きられるようになるためには、「自由」と「多様性」の両方が必要だ。
自分は他者に受け入れられる存在だ、と「尊厳」をもてるようになるには、他者から「承認」された経験が必要だ。子どもは成長の過程で他者と交流し、「試行錯誤」を繰り返して、「尊厳」を得ていく。ところが、「みんな(他者)」のことがよくわからなくなったいまの社会では、安定した「承認」が得られなくなり、安定した「尊厳」も得られなくなった。すると、さらに「みんな」のことがわからなくなるという悪循環が生まれている。