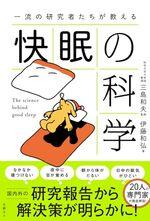40代から衰え始める前頭葉
人間らしさの源泉の老化
いまや日本人の平均年齢は40代後半である。2022年に国連が発表した各国の年齢中央値では、48.7歳で世界第2位だ。アメリカや中国が30代後半、インドやインドネシアは20代後半であることを考えると、日本は超高齢社会の先駆けとなっている。
「40代・50代はまだ若い」と思うのは、「日本全体の平均年齢が上がっているから」ではなかろうか。しかしいくら「若い」と思っても、脳科学的には脳の老化は40代から始まっている。とりわけ深刻なのは「前頭葉の老化」だろう。
前頭葉は大脳の前方にあり、大脳全体の30%を占めていて、役割も多様だ。前頭葉の一部である「前頭連合野」は思考や判断といった情報処理、意欲、情動のコントロール、創造性や社会性などの“人間らしさの源泉”を担っている。
「老人は怒りっぽい」と言われるが、これは前頭葉の「情動のコントロール」がうまく機能しなくなっているからだといえる。
機能低下する日本社会

人間の脳、それも前頭葉は、早い人で40代前半から顕著に縮み始める例もある。
前頭葉は20代に最も遅く「完成」し、真っ先にその機能を低下させる。前頭葉の認知機能のうち情報処理能力や記憶力に至っては18歳頃がピークだという。語彙力などの言語能力は60代から70代まで成長し続けるが、これは例外である。私たちは「20代を過ぎても伸び続ける能力で、低下してゆく能力をなんとか補って日常生活を送っている」のだ。
記憶や言語情報を司る側頭葉や、計算問題を処理する頭頂葉の機能は加齢の影響を受けにくい。90歳を過ぎてもプルーストの小説を読んで、記憶することはできる。しかし、前頭葉の老化は感情の老化だ。その感情のコントロールは、「未知のことがら」に直面して前頭葉が真価を発揮する一例だ。イノベーションにも前頭葉の機能が必要である。
平均年齢が上昇することで、前頭葉の「機能低下」とともに日本社会の「老化」が進んでいるように見える。われわれは脳が衰えていくのを待つほかないのだろうか。
チェックすべき前頭葉の「機能不全」
変化についていけない
前頭葉の能力を低下させないために、まずは自分の状態を確認することから始めよう。そのための7つのポイントからいくつか紹介する。