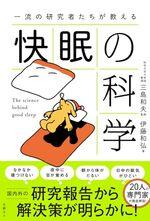【必読ポイント!】 おしゃべりな動物たち
動物たちはおしゃべりだった
動物はさまざまな方法でコミュニケーションを取っているが、意外にも「言葉」を使った方法も多く用いられている。
著者のひとりである鈴木俊貴が専門とするのは、群れで生活する小さな鳥のシジュウカラだ。体のサイズが小さいので、天敵であるタカやヘビに先手を打たれるとやられてしまう。そのため、ある個体が天敵を発見すると、警戒の鳴き声を発する。
危険に対する対処法は天敵ごとに異なる。タカが来たら隠れなくてはならないが、ヘビが木を登ってきているのにじっとしていたら食べられてしまう。
そのためタカの場合は「ヒヒヒ」、ヘビの場合は「ジャージャー」と鳴き声を変えて、群れの仲間が対応できるようにしているのだ。
「ジャージャー」という声が聞こえると、シジュウカラはヘビがいそうな地面や茂みを確認しに行く。鳴き声の録音を流しても、同様の行動を取る。
しかし、これだけでは「ジャージャー」という鳴き声が「茂みを確認せよ」という指示なのか、「ジャージャー」は「ヘビ」のシンボルで、それを聞いたシジュウカラがヘビのイメージを思い浮かべているかは定かではない。
シジュウカラは言葉のイメージを持っている

実験の結果、シジュウカラの「ジャージャー」はヘビのシンボルであることがわかっている。
鈴木は、「ジャージャー」という声を流すと同時に、木の枝に紐をくくりつけ、木の幹沿いに引き上げて動かすという実験を行った。「ジャージャー」という声を流しながら枝を動かすと、シジュウカラはほぼ確実にこの枝をヘビと見間違えて確認しにきたという。しかし別の声を流したときには、同じように枝を動かしても反応しない。つまりシジュウカラは「ジャージャー」という音からヘビのイメージを思い浮かべているため、木の枝をヘビと見間違えてしまうのだ。