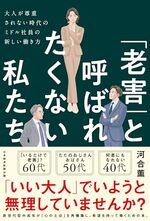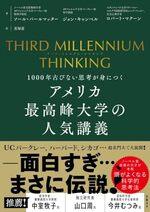ウィンストン・チャーチル
「我々は戦う。岸辺で、上陸地点で、野原で、街路で、丘で」 1940年6月4日 英国院議会にて

チャーチルのこのスピーチは、文句なしに「現代史を動かした」名演説の定番と言えるだろう。名演説とは得てして状況がよいとき、たとえば歴史的な勝利を飾ったときに行われるものだが、この演説は違う。
第2次世界大戦下の1940年、ナチス・ドイツ軍の侵攻はベルギーからフランスへと進んでいた。イギリス軍はフランス軍を支援したが、ドイツに対して屈辱的大敗北を喫してしまう。結果、ヨーロッパ大陸から撤退しなければ、全滅するか数万人が捕虜になってしまうという危機的状況を迎えた。
連合軍はダンケルク海岸からの撤退作戦を計画するが、イギリス軍の軍艦だけではとても全員を救出できない。そこでチャーチルが行ったのがこの演説である。チャーチルは全英国人に向けて「あらゆる船を持つ人は全員ダンケルクに赴き、英軍と仏軍を救出してほしい」と訴えた。その結果、撤退作戦は見事に成功、33万人もの同盟兵が助けられた。
英国民もイギリス軍兵士も、負け戦に意気消沈していた。しかし兵士たちが作戦後に母国に戻ると、国民はこれを大歓迎した。さらにチャーチルの演説がラジオから流れ「さあ、ここからやるぞ!」と一層奮い立った。まさに人の心を動かした演説といえる。
チャーチルはこの演説で、国民の記憶に新しい失敗を挙げた。ドイツの攻撃を劇的に描写し、後悔を煽り、つらかった過去を思い出させた。その上で、今度はそれを総動員で乗り切ったという直近の功績を語る。その後で、この先どう防衛するかという本題に持ち込めば、聞く者の感情はどうしたって揺さぶられることになる。
特筆すべきなのが、首句反復と呼ばれるレトリックのテクニックだ。「我々は戦う。岸辺で、上陸地点で、野原で、街路で、丘で。我々は決して降伏しない。万が一、広く本土が征服され飢えに苦しむことになろうとも、わが帝国は海の向こうでイギリス艦隊に守られつつ、必ずや戦い続けることだろう。神の思し召しにより、新世界が持てる力の全てで旧世界の救済と開放に向かう時まで」――この演説の最終段落では、「we shall」が11回も繰り返されている。ここで力強く決して降伏しないという意志、そしてイギリスがヨーロッパを救うという決断を示したことは、大きく人の心を動かしたのである。
【必読ポイント!】 ウォロディミル・ゼレンスキー
「ウクライナに栄光あれ」2022年3月8日 英国議会・オンラインにて。同12月21日 米国連邦議会にて。

ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、英国議会で行われたスピーチにおいて、チャーチルの演説を引用した。