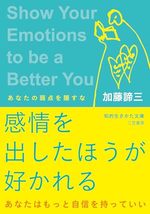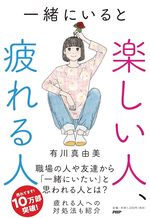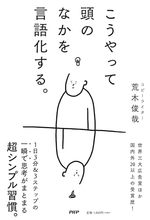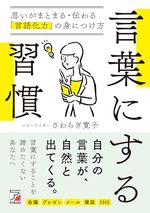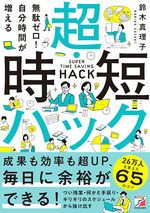なぜ4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか
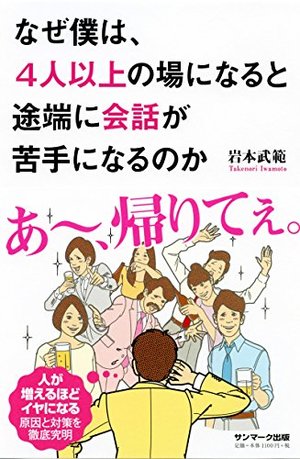
なぜ4人以上の場になると途端に会話が苦手になるのか
著者
著者
岩本武範(いわもと たけのり)
静岡産業大学 教授。工学博士(京都大学)。
1975年生まれ、静岡市出身。
マーケター、データサイエンティスト、行動分析の実務家として20年以上にわたり、「人はなぜ選び、なぜ動くのか」を探究。延べ3000億件を超える行動データ
1000人超のグループインタビューを通して、人間の行動パターンと変容の兆しを読み解いてきた。
現在は大学で教鞭をとるかたわら、教育・都市政策・まちづくりの現場と連携し、「人の幸せ」や「地域の魅力」の見える化を進めている。自治体と協働してウェルビーイング指標の開発や地域データの活用にも取り組み、マーケティング教育やキャリア形成の支援にも力を入れている。
近年は、行動と幸福感の関係性を「ASOBI(心の余裕)」という独自概念でとらえ直し、「Slack Field=動ける余裕のある心と環境」という視点から、人が自然に力を発揮できる条件を明らかにしようとしている。
無理なく話せる、決断できる、前を向ける——その裏には、いつも「余裕」がある。そうした空間や状態を科学的に設計・支援する方法を探るため、国内外で実践と研究を続けている。
静岡産業大学 教授。工学博士(京都大学)。
1975年生まれ、静岡市出身。
マーケター、データサイエンティスト、行動分析の実務家として20年以上にわたり、「人はなぜ選び、なぜ動くのか」を探究。延べ3000億件を超える行動データ
1000人超のグループインタビューを通して、人間の行動パターンと変容の兆しを読み解いてきた。
現在は大学で教鞭をとるかたわら、教育・都市政策・まちづくりの現場と連携し、「人の幸せ」や「地域の魅力」の見える化を進めている。自治体と協働してウェルビーイング指標の開発や地域データの活用にも取り組み、マーケティング教育やキャリア形成の支援にも力を入れている。
近年は、行動と幸福感の関係性を「ASOBI(心の余裕)」という独自概念でとらえ直し、「Slack Field=動ける余裕のある心と環境」という視点から、人が自然に力を発揮できる条件を明らかにしようとしている。
無理なく話せる、決断できる、前を向ける——その裏には、いつも「余裕」がある。そうした空間や状態を科学的に設計・支援する方法を探るため、国内外で実践と研究を続けている。
本書の要点
- 要点1複数になると急に話しづらくなるのは「脳の処理能力」が原因だ。人間の脳は3人までのコミュニケーションは処理できるが、4人になると処理能力を超えてしまう。
- 要点2会話中、脳では主に「前頭葉」が働いている。
- 要点3複数コミュニケーションの場では「2番手」を目指そう。話を振ってもらい、それを誰かにパスする役割は一番おいしいポジションだ。
- 要点4会話の前は、手を「グーパー」して動かそう。前頭葉が活性化され、言葉がスムーズに出てくるようになる。
要約
4人以上になると話しづらくなる理由
「人が増えると話せない」のは脳のせいだった!
少人数だと話せるのに、人が増えると急に話しづらくなるのはなぜか。
世の中には様々なコミュニケーションに関するノウハウがある。しかし、「コミュニケーションが苦手」であることと、「複数いると話しづらくなる」ことは、まったく別問題だと著者は考える。
複数になると話しづらくなる原因は、「脳の処理能力」にある。そもそも、「会話」というものは、言葉と思考の応酬だ。誰かが話すのを聞いてあいづちを打ち、自分も発言する。それに対して相手もまた反応する。こうした作業はすべて脳がおこなっている。会話中、脳はフル稼働で処理しているのだ。
当然、会話の人数が増えると、脳のやるべきことも増える。1対1ならなんとかなっても、複数になると言葉が出てこなくなったり、相手の話にうまく反応できなかったりするのは、脳がパンクしているからだ。
「3」と「4」の間にある壁

v-graphix/gettyimages
脳が「なんかいっぱいある!」と感じて、処理が追いつかなくなる境界。それは、「3」と「4」の間にあると著者は考える。たとえば、「トップ3」という言い方はあるが、「トップ4」はない。また、オリンピックのメダル数、三大欲求、日本三大○○なども、すべて「3」である。
著者はこれまで数多くのグループインタビューを行ってきたが、「3人だと話が盛り上がるのに、4人以上になった途端、沈黙が広がる」という場面に何度も遭遇してきた。

この続きを見るには...
残り3464/4075文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.07.25
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約