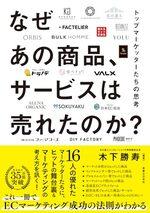プレゼンは「対話」である
なぜ緊張してしまうのか
著者はプレゼンを「対話」だと捉えている。「対話するプレゼン」では、相手の「いまこの瞬間」の要望や疑問をすくい上げ、それに丁寧に答えながら進めていく。
プレゼンで緊張してしまうのは、それを「特別な場」だと考えているからだ。「特別な場だから、何か特別なことをしなければ」という思いが、緊張を生む要因となっている。
その結果、「うまく話さないと」「ちゃんと理解してもらわなければ」「言い間違えてはいけない」と、多くの「ねばならない」に縛られてしまう。特に真面目な人ほど、この状況に陥りやすい。
「特別な場」だから緊張するのなら、プレゼンを「いつもの場」に変えてしまえばよい。つまり、用意したストーリーを叩き台とし、いつものような話し合いの場にしてしまうのだ。
居て、聴いて、語る

著者はかつて劇団四季に所属し、多くのミュージカル作品に出演してきた。「居て、聴いて、語る」は、劇団四季で学んだ教えであり、現在プレゼンを指導する中で原点としている言葉である。
説得力のあるセリフを言うためには、しっかりと準備し、その場に「居る」ことが求められる。そして、相手の言葉や感情をしっかり「聴いて」、そのリアクションとして「語る」。舞台では、この姿勢が欠かせない。
プレゼンが苦手な人は、あらかじめ考えてきたストーリーや資料を、一言一句漏らさず伝えることに懸命になっている。それでは自分のセリフにとらわれ、相手の言葉を聞いていない俳優と変わらない。
「対話するプレゼン」が目指すのは、相手との共感や信頼を築くための「心に響くプレゼン」だ。本書では、7章にわたってそのステップが紹介されるが、次からは第4~6章の「プレゼン前の空気の作り方」「話し方」「問いかけと受け止め」を取り上げる。