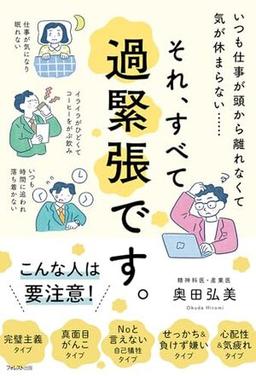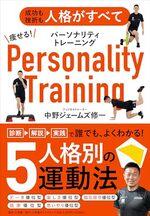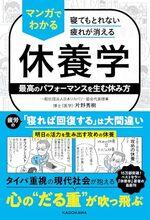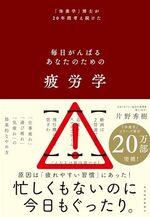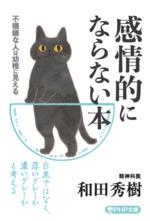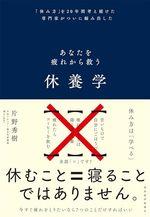過緊張とは何か
Tさんのケース

著者は現在、約20社の企業で嘱託産業医として活動しており、日々の面談のなかで「過緊張」の症状を示す人々と多く出会う。過緊張とは、ストレスの影響により自律神経系の交感神経が過度に緊張した結果、引き起こされる症状の通称だ。
最近面談をしたTさんも、まさに過緊張の症状を示していた。Tさんは、ストレスチェックで高ストレスと判定されたエンジニアである。クライアント案件でトラブルが発生し、2か月にわたり月70時間を超える時間外労働を余儀なくされていた。さらに、クライアント側の担当者の物言いが厳しく、執拗に責められているという。退勤後も相手の言葉が頭から離れず、食欲がないそうだ。仕事のことが気になって就寝前にパソコンやスマートフォンを見てしまい、睡眠時間は短く、眠りは浅くなっていた。
著者はTさんに対し、過緊張という「心身からのイエローサイン」が出ていることを伝え、放置すれば不眠症やうつ病へと進行する危険性が高いことを説明し、改善のための具体的な助言を行った。同時に会社側に対しては、Tさんの業務負担を軽減し、残業および問題となっているクライアント担当者との接触を避けるように申し入れた。
幸いにも、Tさんは過緊張の症状が現れた初期の段階で産業医面談を受けることができ、会社側も迅速に対応したため、深刻な事態には至らなかった。しかしながら、面談に来る時期が遅れたり、会社が産業医の意見を迅速に受け入れなかったりする場合には、症状が進行して休職に至るケースも少なくない。また、本人が体調不良を認めずに無理をして働き続けた結果、突然倒れるケースもある。
過緊張は決して放置してはいけない。あらゆる病気は「早期発見、早期治療」が鉄則なのだ。
過緊張が起こる仕組み
ここでは、過緊張が生じるメカニズムについて解説したい。
人間の身体には、基本的な生命維持活動を担う重要な神経系として「自律神経系」がある。この神経系は全身に張り巡らされており、血液の循環や呼吸、ホルモン分泌、排せつ、体温調節といった、生命維持に不可欠な機能をコントロールしている。
自律神経系は、交感神経系と副交感神経系という2つの系統から成り立っている。交感神経系は、主に身体が活動状態にあるときに優位となり、一方の副交感神経系は、休息やリラックス時に働きが強まる神経系である。
私たちが仕事や活動に取り組んでいる「ON」の時間帯には、交感神経系が優位となり、俊敏な行動や的確な思考が可能となる。そして夕方以降の「OFF」の時間帯になると、副交感神経系が主導権を握り、心身はリラックスモードへと移行していく。こうして身体は、自動的にONとOFFを切り替え、エネルギーのバランスを保っているのである。
ところが、心理的あるいは身体的なストレスが強くかかると、この自律神経のバランスが崩れ、交感神経系の働きが過剰となる。その結果として「過緊張状態」が引き起こされるのだ。
【必読ポイント!】 過緊張のセルフケア法
基本のセルフケアは3種類

過緊張へのセルフケアは「休息(Rest)」「リラクゼーション(Relaxation)」「レクリエーション(Recreation)」の3つに分類される。これらはレスト→リラクゼーション→レクリエーションの順で取り組むことが重要だ。それぞれについて解説する。