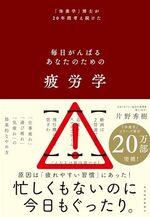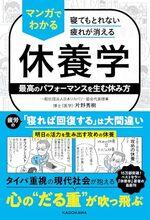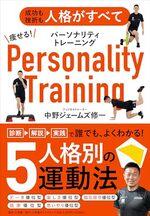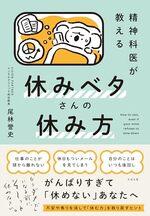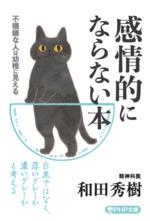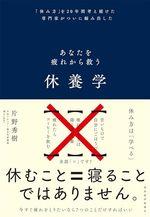疲れとセロトニン
慢性疲労の原因は「脳」にある
体にこれといった異常は見られず、十分な休養もとっているはずなのに、目覚めが悪く、体調はすぐれないし、やる気も湧いてこない――。
このような慢性的な疲労感の根本的な原因は、「脳」にある。
脳内には、「ノルアドレナリン神経」と「セロトニン神経」という、覚醒を司る神経が存在している。これら2つの神経は、起床と同時に活性化し、大脳を覚醒させるとともに、気分の落ち込みをやわらげ、身体を活動モードに切り替える役割を担っている。さらに、自律神経を「休息の副交感神経」から「活動の交感神経」に切り替え、体温や血圧を上げ、代謝を活発にする役割も果たす。
しかしながら、これらの神経が「脳疲労」によってうまく機能しなくなると、目覚めた直後から疲労感が抜けず、意欲がわかず、気分も沈みがちになり、体も思うように動かなくなってしまう。
「頭の疲れ」と「心の疲れ」

脳疲労には、大きく分けて2種類ある。
1つ目は、大脳を酷使することで生じる「頭の疲れ」だ。「頭の疲れ」が現れると、思考が鈍くなるだけでなく、寝つきにくくなる。その主な要因は、パソコンやスマートフォンといったデジタル機器の長時間利用だ。
2つ目は、「心の疲れ」だ。こちらは大脳辺縁系、中でも「扁桃体」という領域が関係している。精神的ストレスがかかると、扁桃体が過剰に反応し、気分の落ち込みや意欲の低下を引き起こすのだ。
注目すべきは、「頭の疲れ」が「心の疲れ」を引き起こす点だ。
デジタル機器に依存した生活を送っていると、睡眠の質が悪くなり、よく眠れなくなる。眠れないと、ついインターネットやゲームに手が伸び、翌朝は寝不足。頭がすっきりせず、体調も整わない……。こうした悪循環が、やがて「心の疲労」へとつながっていくのだ。
セロトニンを分泌させる2つの習慣
「セロトニン神経」の機能が低下すると、良質な睡眠や朝のすっきりとした目覚めが得られにくくなるばかりか、自律神経失調症や慢性疼痛、うつ病などを引き起こす原因になる。「心の疲れ」を深刻化させないためには、セロトニン神経の働きを常に活発に保つ努力が欠かせない。
そのために有効なのが、太陽光を浴びることと体を動かすことの2つである。
朝になってもカーテンを閉め切ったまま、寝転んでデジタル機器に没頭するような生活を続けていれば、セロトニン神経は十分に働かず、やがて正常に機能しなくなってしまう。その結果、心身にさまざまな不調が現れるようになる。










![[新版]人生を変えるモーニングメソッド](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F4229_cover_150.jpg&w=3840&q=75)