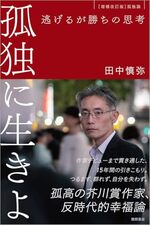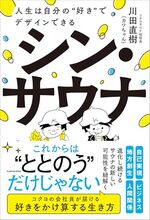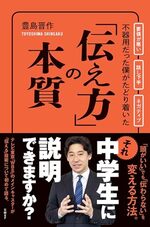リサーチ・クエスチョンとは何か?
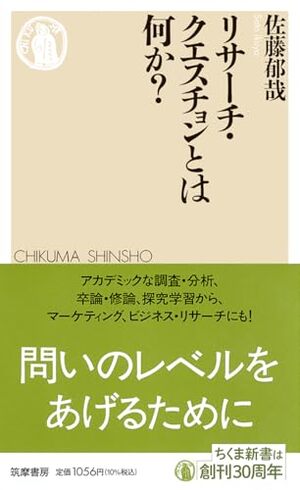
リサーチ・クエスチョンとは何か?
著者
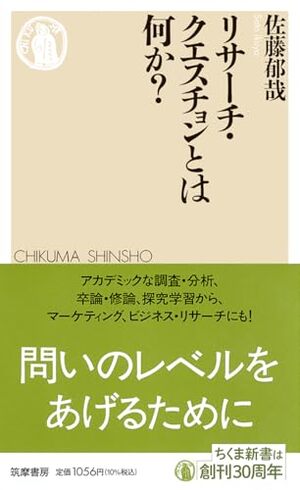
著者
佐藤郁哉(さとう いくや)
1955年、宮城県生まれ。77年、東京大学文学部卒業。84年、東北大学大学院博士課程中退。86年、シカゴ大学大学院修了(Ph.D.)。一橋大学大学院商学研究科教授、プリンストン大学客員研究員、オックスフォード大学客員研究員、同志社大学教授などを経て現在、一橋大学名誉教授。専門は経営組織論・社会調査方法論。主な著作に、『暴走族のエスノグラフィー』(新曜社、国際交通安全学会賞)、『現代演劇のフィールドワーク』(東京大学出版会、日経・経済図書文化賞)、『社会調査の考え方[上][下]』(東京大学出版会)、『大学改革の迷走』(ちくま新書)、『はじめての経営学 ビジネス・リサーチ』(東洋経済新報社)、訳書に『面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方(第2版)』(白桃書房)などがある。
1955年、宮城県生まれ。77年、東京大学文学部卒業。84年、東北大学大学院博士課程中退。86年、シカゴ大学大学院修了(Ph.D.)。一橋大学大学院商学研究科教授、プリンストン大学客員研究員、オックスフォード大学客員研究員、同志社大学教授などを経て現在、一橋大学名誉教授。専門は経営組織論・社会調査方法論。主な著作に、『暴走族のエスノグラフィー』(新曜社、国際交通安全学会賞)、『現代演劇のフィールドワーク』(東京大学出版会、日経・経済図書文化賞)、『社会調査の考え方[上][下]』(東京大学出版会)、『大学改革の迷走』(ちくま新書)、『はじめての経営学 ビジネス・リサーチ』(東洋経済新報社)、訳書に『面白くて刺激的な論文のためのリサーチ・クエスチョンの作り方と育て方(第2版)』(白桃書房)などがある。
本書の要点
- 要点1報告書や論文を作成する際、型通りに完成させようとするだけでなく、調査・研究の途中における問いの試行錯誤の経緯を大切にすることで、筋の良いリサーチ・クエスチョンを立てられるようになる。
- 要点2リサーチ・クエスチョンは、「5W1H」ではなく、Whatの問い(どうなっているのか?)とWhyの問い(なぜ、そうなっているのか?)に、How toの問い(どうすれば良いか?)を加えた「2W1H」の間を何度も往復することで洗練されていく。
- 要点3筋の良いリサーチ・クエスチョンは、意義、実証可能性、実行可能性の3つの条件を全て満たすものである。
要約
リサーチ・クエスチョンとはどのようなものか
論文はペテンである

PixelsEffect/gettyimages
「科学論文は一種のペテンである」という言葉がある。これはノーベル生理学・医学賞を受賞したピーター・メダワーという生物学者の弁であるが、確かに典型的な論文の構成には、実際の研究の手順と経緯に関して大きな誤解を招きかねないような特徴がある。特に、リサーチ・クエスチョンに関する誤解は深刻だ。
実証的手法による研究論文は、「序論・方法・結果・考察(IMRAD)」という形式をとる場合が多い。しかし、このように直線的なプロセスへと整理された表面上の「型」だけに囚われると、試行錯誤と紆余曲折を経て行われる実際の調査のプロセスとの間に大きなギャップが生じてしまう。発表された論文では、調査で得られた最終的な結論だけを効率的に報告するために、調査中の経緯は省略される。実際の調査プロセスと異なるという意味では、論文はフィクションでありペテンであるとも言える。
論文を書けるようになるために、初学者は研究を論文の型に沿った形でまとめる「上手なウソのつきかた」を身につける必要がある。しかしそれだけでは、論文を効率的に量産できるようになるかもしれないが、面白い研究を期待しづらくなる。革新的な研究とは、枠からはみ出た斬新なアイデアや、「セレンディピティ」と呼ばれる予想外の発見から生まれてくることが多いからだ。基本的な型に沿った論文を書くときにも、試行錯誤と右往左往のプロセスを活かし、セレンディピティを追求できる余地を残すことで、「筋の良い」リサーチ・クエスチョンを作り、育てられるようになるだろう。

この続きを見るには...
残り3772/4443文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.07.20
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約