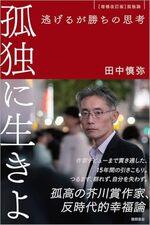【必読ポイント!】 お米でたどる日本の歩み
水田稲作の伝来と広がり
「水田稲作(田んぼでの稲作)」は、縄文時代晩期までに中国から日本へ伝わったと考えられている。
弥生時代に稲作が広まると、お米や土地、水を巡る争いが生じ、各地に多くの富(お米)を手に入れた「豪族」が生まれた。
権力者たちは自らの力を示すため、生前から巨大な墓(古墳)を築かせた。古墳の建設には膨大な労働力と食料が求められたため、当時の権力者たちは人々を動員し、土地を開墾して田んぼを広げていった。
日本最大の古墳は、大阪府堺市の「大仙陵古墳」である。この古墳の工事期間は16年にも及び、ピーク時には1日に3000人もの人々が働いていたと推定されている。
大規模な古墳づくりに従事した人々の食を支えるため、米の生産量は増加し、古墳を囲む堀が田んぼの用水路として活用されるなど、古墳は結果として稲作と米食文化の発展を後押しする役割を果たした。
中央集権とともに始まった「お米=税」制度

701年、日本で最初の体系的な法律「大宝律令」が制定された。それ以前は各地の豪族が土地や人々を支配していたが、この法律によって、政治権力は中央政府に集中することとなった。
そして、土地と人々を国が管理するという「公地公民」の方針のもと、お米を税として納める「班田収授法」が義務化された。6歳以上の男女1人につき、「口分田」と呼ばれる一定面積の田んぼが与えられ、そこで収穫されたお米を納める仕組みである。
お米が税に選ばれた背景には、寒冷な東北地方でも稲作が可能だったこと、栄養価の高さ、もみのままで長期保存ができたことなどがあったようだ。この時期に始まった「お米=税」という制度は、1873年の「地租改正」で税が米から金銭に切り替わるまで、およそ1200年にわたり続いた。