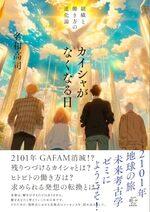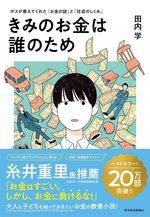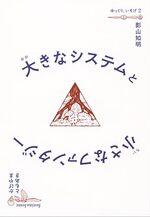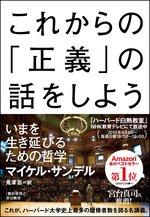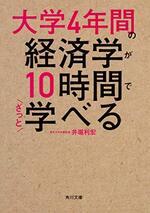伝わらない最大の原因
誰もが話を聞いてほしい

8割くらいの人は、「自分が話したいこと」を「自己満足のため」に話している。それがつまらない話や長い話となる。不満や楽しい体験を誰かと共有したいと思っても、それは相手が聞きたい話とは限らない。
「本当に伝わる話し方をする人は、自分ではなく『聞き手を満足させること』を最優先に」するのだ。つまり伝える力とは、「聞き手を満足させる力」なのである。
話をしている人はたいてい自分自身を客観視できないため、自分が快感の赴くままにつまらない話をしていることに気づけない。時間的な余裕がなくて聞き手のことにまで頭が回らない場合もある。
ほとんどの人は「『自分の話を聞いてもらいたい』という願望」を強く抱いているし、他者からの承認を求めている。自分もそういう人間なのだということを自覚するところがスタート地点だ。
まずは、「スマホのカメラで自分が話している動画を撮影して見返すこと」を何度も繰り返してみよう。そのときの声色や表情が、「あなたが人に何かを伝えているときの姿」だ。この「スマホ自己診断」を実際に試すかどうかで、伝える力は雲泥の差となる。本を読むだけでは自転車の乗り方が身につかないのと同じだ。
本書で紹介する方法は、どれも練習が大切となる。そして、実際に伝えるには相手が必要だ。一人での練習に閉じることなく、プレゼンや会話などで経験を積まなくてはならない。
【必読ポイント!】 「伝える」技術
「相手が聞きたいこと」を伝える
相手に伝えるためのファーストステップは、シンプルに「『相手が聞きたいこと』を話すこと」だ。多くの人は「『自分が他人から褒められている』という情報」を知りたがっているので、「まず相手を褒めること」が大事である。そうして承認欲求が満たされれば、話を聞いてもらえる可能性が高まる。評価の理由をできるだけ具体的にすると、お世辞だと思われずに深い満足感を与えられる。
つまらない話はたいてい、「過去に起こったこと」だ。現在を生きている聞き手にとって、いま有益となる情報のほうが知りたい。過去の話であっても、「再現可能な方法が含まれているかどうか」が鍵となる。過去の話にもとづいて伝えたいことがあるなら、成功ではなく失敗を話すほうが引きつけられる。ここでも、「同じ失敗をしないための情報」を具体的に述べることがコツだ。「きちんと期限を守れ」というようにただ叱責するより、過去の失敗とそこから得た学びを交えたほうが、聞いているほうも前向きに捉えることができる。
後輩に経験を伝えるとき、そこには「『昔の自分の努力や成功を知ってもらいたい』という承認欲求」が顔をのぞかせている。「過去を肯定したい」という思いから苦い記憶を伝える場合も、それを吐露することで理解を示してくれることを望んでいる。いずれも、「自己満足のための話」なのだ、ということを肝に銘じておきたい。
「引き算」して伝える

新製品をアピールしようとして、伝えたいことを全部盛り込んでしまい、時間が足りなくなる。そういう失敗はよくあることだろう。
人間は一度にたくさんのことを理解可能なようにはできていない。「話す内容を減らす、つまり『引き算』すること」が大切だ。