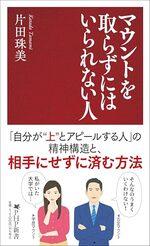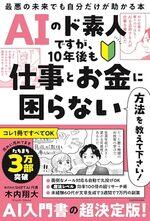若者が実践する「自分軸の働き方」
転職前提で入社する若者たち
リクルートの調査(2022年)によれば、20代の約8割が転職を視野に入れている。
「現在在籍する会社でどれだけ働き続けたいか」という問いに対し、「定年・引退まで働き続けたい」と答えたのはわずか2割(20.8%)。「20年」は5.4%、「10年」は13.7%、「5年」は15.6 %と、勤務年数が短いほど割合が高くなる。「2.3年」と回答した人は約3割(28.3%)に達し、「すぐにでも退職したい」という声も16.2%あった。
さらに、学情の調査(2023年)では、就職する前から約6割が転職を前提として就職しているという結果も出ている。
キャリアは「会社に委ねるもの」ではなく「自分で選ぶ」時代

会社には「人事権」がある。それゆえ会社員は、本人の意志に関係なく、会社の都合で異動させられる。こうした人事異動に従っていては、自らのキャリアを築くのは難しい。
そのような背景から近年、注目されつつあるのが「キャリア権」という概念である。
キャリア権とは、自分自身でキャリアを築く権利のことを指す。多くの経験を積んでゼネラリストを目指すのも、一つの専門を極めるのも、個人が選択するべきだという考え方である。
キャリア権の概念がなかった時代には、人事異動はある種やむを得ない制度とされていた。
しかし、2010年頃からは「特定総合職」という制度が導入され、「総合職よりも給与は2~3割低いが、転勤は関東一円の1都6県に限定」といった別枠のキャリアコースが生まれてきた。
また、近年では「配属ガチャ」という言葉も一般化し、配属の仕組みを見直す企業も出てきている。たとえば三井住友銀行では、2025年4月入社の新卒社員から、最短2年目で海外配属を確約する採用コースを新設した。「配属ガチャ」を排除することで、英語力を備えた優秀な人材を確保する狙いがあるという。
「配属ガチャ」や「人事異動」によって、企業はゼネラリストを育成し、将来的な管理職へのステップを踏ませようとしてきた。
しかし、現在では若者の約8割が転職を視野に入れ、6割が転職前提で就職し、3割が3年以内に離職しているのが実情である。管理職にならないのであれば、ゼネラリストとしての経験は報われにくい。今後は、個々人が自らのキャリアを考え、キャリア権を軸に行動する時代となっていくだろう。
「キャリア権」を尊重し、自律的なキャリア形成を支援する会社づくりこそが、今後は求められるのではないだろうか。
若者とのコミュニケーションの極意
3年で転職するルールを前提に

同じ職場で働く若者たちと、どのようにコミュニケーションを取っていけばよいのか。