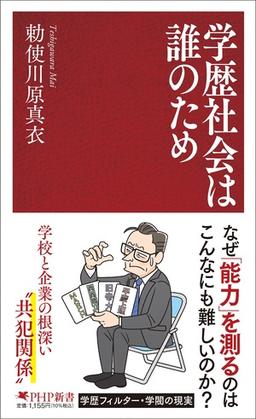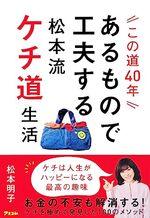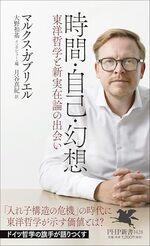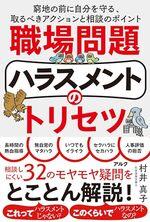学歴論争とは何だったのか
こうして「能力」が指標になった
「学歴」とは学校の経歴を示す言葉であり、それ以上でも以下でもない。しかし、そこに「主義」という言葉をつけて「学歴主義」とすると、言葉の印象はガラリと変わる。学歴主義とは学歴が「人の価値」の基準とされる価値観だ。そしてこの主義に社会が合意した状態が「学歴社会」といえるだろう。
「人の価値を評価する」。ではそもそもなぜ「人の価値」を「評価」しなくてはならないのだろうか。その点を、能力主義の基本概念に注目しながらもう少し掘り下げてみよう。
お金、土地、食料。こうしたリソースは有限なので、分け合って生きなければならない。問題はそれをどのように配分するかだ。身分制度の時代は権力者に多く献上しようというのがまかり通っていた。しかし、社会が進歩してくると、「生まれ」で持つものと持たざる者が決まってしまうのは不平等なのでは、という疑問が湧いてくる。
近代に入ると身分制度は廃止され、資源をどう配分すれば不満が出ないかという課題が出てきた。この流れを受けて、努力を含む出来(=能力)によって分け合い、多寡を決めようとする能力主義が誕生したのである。「能力」の高い人こそが、「価値」の高い人であり、そうした人が多くをもらうべきである――というロジックは今や我々の社会システムの中心的な運用基準となっている。
学校と能力主義

ここで一つの疑問が生じる。能力の多寡は、いったい誰がどのようにして計測するのだろうか。「能力」「コミュ力」「リーダーシップ」「主体性」等々、能力に関連する言葉は数多くあれ、その実態は目には見えないし、そもそも同じイメージを共有できているのかもわからない。能力なるものを測定し、個人の有能さを客観的に証明するというのは、最初からSFのような物語なのである。しかし、多くを得るべき人とそうでない人を決めなければ分配は立ち行かない。では現代社会は何を測ったことにして成り立っているのだろうか。