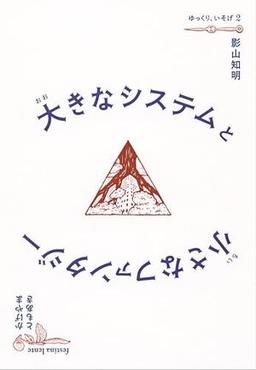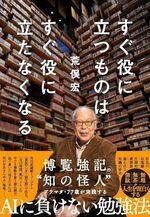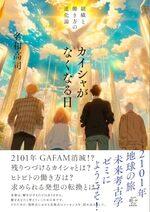自分の時間を生きる
△(リザルトパラダイム)と▽(プロセスパラダイム)

今の社会はピラミッド状(△)にできている。組織や会社では、労力やコスト、時間をできるだけ少なくすることが求められる。このような成果(リザルト)を先に決め、それに最短距離で近づこうとするやり方は「リザルトパラダイム」と表現されることがある。
しかし、一人一人のいのちの形は生まれながらにして違うから、一定の型にはめようとするとうまくいかなくなる。△(リザルトパラダイム)の社会づくりに対して、▽(逆ピラミッド状)の社会づくりを考えられないかと著者は提案する。▽の社会づくりとは、成果を事前に定義せず、一人一人の存在や一つ一つのしごと、関係性、偶発性、縁を大事にして、行き着く先をオープンに考えるという意味で「プロセスパラダイム」と表現される。
カフェの運営では、レシピやスケジュールなどが固定化され、マニュアル化されていく。マニュアルがあれば楽に働けるようになり、仕事の質も安定する。しかし、マニュアルを前提として働くことに慣れてしまうと、固定化した働き方を変えられなくなる。年月を重ねたお店が停滞する罠はここにある。小さな組織ならばマニュアルやシステムを変えるのは難しくないが、大企業では、決められたように仕事をしなければならないだろう。
ミヒャエル・エンデの『モモ』では、一人一人が自分の時間を持っていて、ほんとうの持ち主から切りはなされると時間は死んでしまうとされている。では、私たちは自分の時間を「生きた時間」として生きることができているのだろうか。
会社や組織で働き、自分の意思ではなく組織として「決められたこと」に従って仕事をしているとき、私たちは「自分の時間」を差し出して「組織の時間」を生きている。しかしそれは、エンデの言葉に従えば「死んだ時間」だ。現代は、それだけ自分の時間を生きるのが難しい時代である。
△(リザルトパラダイム)を支えるのは、様々なシステムと制度であり、組織の時間を生きるということはシステムの時間を生きるということだ。では、自分の時間を生きるにはどうすればいいのか。こどもたちは、今この瞬間の「やってみたい」「いやだ」といった情動に身を任せて生きている。大人たちの中にも、こどもだった自分が眠っているはずだ。著者の店・クルミドコーヒーには、こどもの自分に帰って自分の時間を過ごしてもらいたいという思いが込められている。