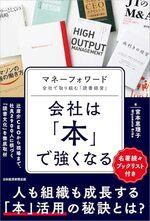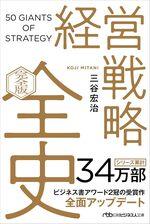競争しない競争戦略
競争しない3つの戦略
本書では、やみくもに売上やシェアを増やすことよりも「競争しない状態」を作ることによって利益率を高められるという「競争しない競争戦略」を紹介していく。競争しない戦略を考えるうえでは、業界のリーダー企業の戦略を分析することが必要だ。リーダー企業は、経営資源の質・量ともに最大であるため、敵にまわすと一番脅威になるからだ。
リーダー企業の戦略定石としては、市場のパイを拡大させる「周辺需要拡大」、チャレンジャーの差別化戦略を模倣して差別化効果を無にする「同質化政策」、安売り競争に応じない「非価格対応」、そして、利益が最も高くなる売上でのシェアを維持する「最適シェア維持」という4つの方法がある。とりわけ、リーダー企業が一番対抗しやすいのが「同質化政策」であり、日本企業はそれを得意としてきた。
そこで、経営資源が少ない企業が生き残るためには、強い者と戦わない「棲み分け」と、強い者と「共生する」方法という2つの選択肢がある。棲み分けは、「ニッチ戦略」と「不協和(ジレンマ)戦略」に、共生は「協調戦略」に類型化することができる。この3つの戦略の詳細をこれから明らかにする。
【必読ポイント!】 ニッチ戦略
リーダー企業の参入を防ぐニッチ戦略

ニッチ戦略とは、「競合他社との直接競争を避け、棲み分けした特定市場に資源を集中する戦略」のことである。これは、市場規模が小さすぎて、リーダー企業の高い固定費により赤字になってしまう場合や、市場開拓のための経営資源が特殊で、リーダー企業がその資源を今から保有するのは割に合わない場合に可能になる。
ニッチ戦略をとるには、リーダー企業を参入させないことが前提になる。参入を防ぐには、「市場規模をあまり大きくしない」、「利益率をあまり高くしない」、「市場を急速に立ち上げない」という戦略が有効だ。これらは、大手企業で求められることの真逆だといえる。
「質」と「量」の軸から考える
ニッチ戦略は、参入障壁を高める質的コントロールと、市場規模の量的コントロールの2つが武器となる。前者については、リーダーがカバーできていない資源をテコに、その分野に絞って事業を行う「質的限定」という方法がある。一方、リーダー企業にとって小さすぎる市場を開拓し、その分野に集中することを「量的限定」と呼ぶ。
この質的限定と量的限定の2軸を組み合わせると、ニッチ戦略を考えるマトリックスを描くことができる。このうち、量的にも質的にも限定が低いゾーンは、リーダー企業に同質化される可能性が高いため除外すると、ニッチ戦略は次の3つに分類できる。それぞれの戦略をさらに細分化した戦略の概要と、いくつかの具体例を紹介しよう。
質限定のニッチ戦略

「技術ニッチ」:リーダー企業の追随を許さない高い技術によって、市場の攻略を防ぐ。例えば、上場企業の開示業務に特化するプロネクサスは、有価証券報告書の印刷において、改ざんされない技術を磨き、正確性とセキュリティへの強いこだわりを持っている。開示書類を印刷するだけでなく、開示の前工程から企業に入り込んだ「ディスクロージャーのプロセスを支援するサービスプロバイダー」となることで、大手の競合が参入できない状態を作っている。
「チャネル・ニッチ」:リーダーが追随できないチャネルを押さえ、それを通じて限られた市場の寡占を作る。