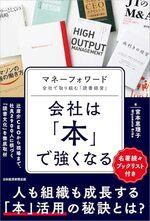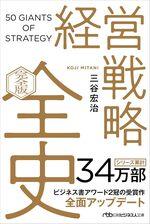【必読ポイント!】 なぜ町の電器屋さんが20年連続黒字なのか?
お客さんが求めているもの

ヤマグチは、売り場面積430平米ほどの町の小さな電器屋である。修理センターを除くと1店舗しかなく、その店舗もターミナル駅の町田駅から約4.5キロメートル離れた住宅街の中に立地している。また、原則値引きをしないため、電化製品の値段は高く、競合となる大手量販店は町田駅周辺に6店もある。
これだけ聞くと、今にも潰れてしまうのではないかと心配しそうになるが、ヤマグチはこのような悪条件にもかかわらずしっかり利益を上げているという。2015年9月期には20年連続で黒字を達成し、粗利益率は40%という驚異的な数字をたたき出している。
なぜヤマグチはこのような高収益店を作ることができたのか? それはひとえにヤマグチが、価格ではなく顧客サービスを徹底する方針に切り替えたからである。価格で大手に競り勝つことは難しい。競争に持ち込んでもすぐにこちらが疲弊してしまうことは目に見えていた。悩んだ末にヤマグチが導き出したのが、値引きしないかわりに、家電の設置や修理・不具合の点検などサービスを徹底し、地元密着型で一人ひとりのお客さんを大切にするという方針である。
ヤマグチのお客さんは高齢者が多い。60代~70代がメインで、80代~90代のお客さんも珍しくない。高齢になると、車で家電を買いに行ったり、壊れた家電を修理に出したり、電球を取り替えるといった、若いころには当たり前にできていたことが難しくなる。そんなとき重宝されるのが、ヤマグチの御用聞きサービスだ。ある程度財布にゆとりがある高齢者にとっては、困りごとを解決してくれるのであれば、正規料金で家電を買うことはさほど重要ではない。
ヤマグチでは以前から訪問営業を行っていたものの、エリアを限定していなかったため、1日に回れるのは3~4世帯だけだった。また、せっかく頼まれても、翌日以降にしか伺えないことがよくあったという。
しかし、経営が危機に瀕した20年ほど前、全面的にサービスを見直し、訪問エリアを車で1時間以内に駆けつけられる町田市と相模原市の一部に限定した。すると、お客さんから連絡があったときにはすぐに「トンデ」行けるようになり、1日に訪問できる世帯数も格段に多くなった。
お客さんの小さな困りごとから別の商談に進むこともしばしばある。何かあったときにはすぐに駆けつけ、普段から信頼関係を構築しておくことが非常に大事であると学んだ。
店の規模や数を絶対に拡張しないわけ

ヤマグチは2015年に町田街道の拡張工事にともない、旧店から立ち退かざるをえなくなってしまった。そこで、そこから少し離れたところに新店をオープンした。これを見たお客さんの中には、ヤマグチが多店舗展開を始めたのかと勘違いした人もいたが、社長は1店舗のみと心に決めているという。理由は明確で、個々のお客さんに対するきめ細かいサービスを実現するためだ。社員40人ほどのヤマグチで多店舗化を図ろうとすると、新店舗スタッフの採用や研修が中途半端になってしまい、社長としても目が行き届かなくなる恐れがある。それなら、既存のお客さんのために徹底的にサービスの向上に努めたほうがよいと考えているのだ。山口社長がこのような経営判断を行う背景には、実は20年ほど前の失敗経験がある。