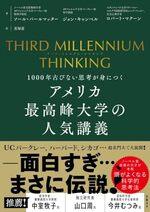日本文化の正体は「変化するもの」にある
ジャパン・フィルター

結論を先にいえば、日本文化の正体は、日本人が信じる神や仏、日本人が愛してきた和歌や国文学そのものにあるのではない。日本文化の正体は「変化するもの」にある。すなわち歌舞伎、日本画、セーラー服やアニメが「変化するところ」に、日本文化の核心があらわれる。
したがって、紋切り型の「ワビ・サビ」の説明や、「フジヤマ・巨人の星・スーパーマリオ」などの表面的な解説だけでは、日本文化の真髄を捉えることは決してできない。いったんは日本神話や昭和歌謡、劇画などに目を凝らし、そこに浸って日本の歴史文化の「変化の境目」をよく知る必要がある。
日本文化の正体、すなわち日本独自の哲学や美の核心を知るためには、そのための切り口が必要となる。これを「ジャパン・フィルター」と呼ぶ。ジャパン・フィルターという手がかりによって、私たちは日本文化をよりよく理解できるのである。
日本の神は「ゲストの神」だった
「柱の文化」から始まる古代日本
重要なジャパン・フィルターのひとつとして、「客神(きゃくしん)フィルター」がある。古来、日本における神は客神、すなわち「ゲストの神」と考えられてきた。これはユダヤ・キリスト教の「神は唯一神であるとともにホストの神である(そのため、彼らは「主よ」と祈る)」とは真逆の思想である。日本の神々は常世から「やってくる神」であり、そのあとさっさと「帰っていく神」である。すなわち客として「迎える神」であり、「送られる神」であった。
ではなぜ日本人は、客神という独特の思想を持つに至ったのか。そのルーツとして、古代日本が「柱の文化」であったことに注目したい。日本人は神のことを「御柱(みはしら)」と読んだり、神の数を「柱」で数えたりしてきた。こうしたことからもわかるとおり、神と柱には切っても切れない関係がある。
そもそも日本人は、何かを始めるときに「柱を立てる」ことを大事にしてきた。村をおこすときも、その中心に一本の柱を立てることからはじめた。これを「村立て」と呼ぶ。『古事記』『日本書紀』などの神話の世界では、日本の天地開闢のいきさつは「国立て」という行為で説明されている。
現代でも、建築工事を始める際には地鎮祭を行う。地鎮祭はその土地の一角の四隅に四本の柱を立て、そこにしめ縄を回して祝詞(のりと)を奏上することで、工事中の無事を祈る。ここに日本の「はじまり」についての考え方が再現されているといえよう。
このように日本人にとって「柱を立てる」という行為は、「村立て」から「国づくり」に至るまで、何らかの共同体をはじめるにあたって不可欠なものであった。
客として迎えられる神

地鎮祭のように四本の柱を立ててしめ縄を回すことで、その場所を新たなスタートの儀式で示すことを「結界する」という。古代の日本人は、結界することによってその中に神を呼び込もうと考えた。だから四方四界を区切るために柱を立てた。だがそこには結界があるばかりで、ほかにはなにもない。そしてなにもないからこそ、そこに神々が降臨すると考えたのだ。
つまり日本人にとっての神は、定位置にいる神でも常在する神でもなく、結界された場所に迎えられ、送られる神であった。このように日本の客神という考え方は、「柱を立てる」という共同体の原点と綿密に関係している。
どのように海外文化を受容してきたか
仮名の出現という文明的大事件
歴史上、日本のコンセプトの多くが「和漢の境(さかい)」をまたぐことによって成立してきた。中国(漢)と日本(和)の交流が融合するなかで、日本独自の表現や認知様式が形成され、独特な価値観をつくってきたのである。
たとえば1万~2万種類もあった漢字を輸入した際も、