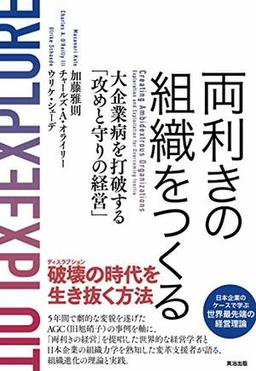いま必要な組織経営論
これまでの組織改革に欠けていたこと
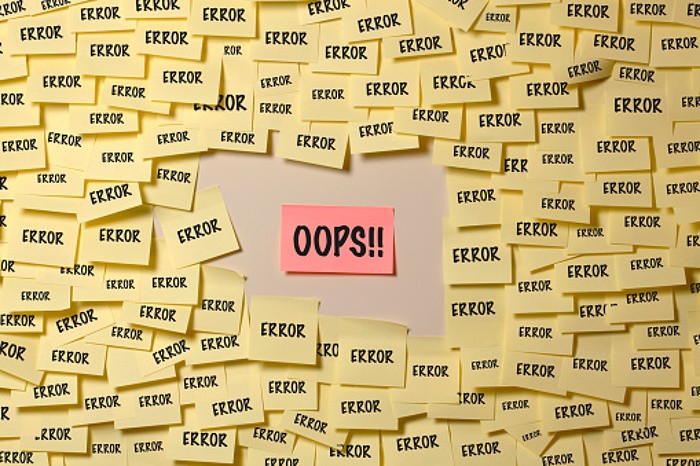
市場環境の急激な変化、デジタル技術を中心としたディスラプション、価値観の多様化など、日本はいまさまざまな変化に直面している。そのような環境にもかかわらず、これまで慣れ親しんだやり方を変えることができない、いわゆる大企業病に蝕まれている日本企業は多い。
その原因は大きく分けて2つある。1つは、経営者が組織や人材についてあまり関心を持っていないパターンだ。この要因として、終身雇用制度の下、総じて従業員の離職率が低く、組織改善の必要性を感じにくかったことが挙げられる。彼らにはどうしても「社員がいきいきと働ける」「風通しのよい企業文化」といった話題が、甘っちょろく幼稚な話に感じてしまうのだ。
もう1つは、戦略性を欠いたまま、組織論だけが語られるパターンだ。理想の組織モデルや働き方の多様化など、さまざまな組織論を語りつつも、それらが事業戦略や経営視点に結びついていない。これはとりわけミドル層に多く見られる傾向である。
つまり経営陣が戦略論に偏って経営を考える一方で、組織や人に関心を持つミドル層が戦略的な視点を持っていないというチグハグな状況が多く見られるのだ。これでは「組織が変わる」ことへの共通イメージなど持てるわけがない。
組織カルチャー変革のためのアプローチ
組織を語る際に大切なのは、組織と戦略の両方に目を向けた、組織経営論という視点だ。戦略と組織は車の両輪に当たり、両者がかみ合うことではじめて機能する。つまり戦略論と組織論をバラバラに議論していても意味がない。
両利きの経営とは、既存事業を維持しながら新規事業を生み出すという戦略論であるだけでなく、「それを可能にするために組織はどうあるべきか」という組織論としての面も併せ持つ組織経営論である。その核心は、組織能力の形成を可能とする「組織カルチャー」のマネジメントにある。本書における組織カルチャーとは、いわゆる社風や組織のDNA、組織風土といった抽象的な概念ではなく、組織で期待される「仕事のやり方」のことだ。この組織カルチャーこそが、最も真似されにくい競争力の源泉となる。
しかし組織カルチャーを変えるのは、途方もなく難しいことだ。多くの日本企業経営者は、組織カルチャーを変えるにはボトムアップでなければならないと口を揃える。一方で外資系を経験した経営者は、トップダウンでなければ変えられないと考えることが多いようだ。だが本書で提案されるアプローチは、そのどちらでもない。
「変革は経営者によるトップダウンとミドル・若手からのボトムアップがミートするところで起こる」というのが著者たちの主張だ。オライリー氏の前著『両利きの経営』では、リーダーシップに最も重きが置かれていたのに対し、本書では「トップダウンとボトムアップの両方が必要である」という視点が重視されている。
両利きの経営
コングルエンス・モデル

両利きの経営とは、「既存事業を深堀りする能力」と「新規事業を探索する能力」、そしてこれら相矛盾する能力を併存させる組織能力の獲得を目指すものだ。しかしそもそも組織能力とはいったい何だろうか。著者たちはこの組織能力を読み解く視点として、「コングルエンス・モデル」を紹介している。
コングルエンス・モデルは、ダイナミックな活動体である組織を「KSF」「人材」「公式の組織」「組織カルチャー」という4つの基本要素から捉える。順を追って説明しよう。