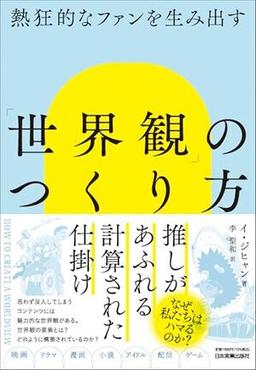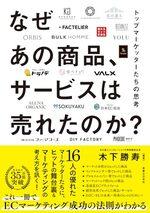世界観とは何か
実在しそうな架空の世界

「世界観」とは何か。本書では世界観を、現実とは異なる要素でつくられた「架空の世界」、およびその世界を構築する「世界設定」と位置づける。ここでは、映画『ハワード・ザ・ダック』(1986年)を例に、世界観について説明したい。
主人公は、ドナルドダックにそっくりなアヒルのハワードである。しかし、ドナルドとは異なり、無愛想でふてぶてしく、しかも他の星からやってきた異星人という設定だ。映画の登場人物たちは、この“人語を話すアヒル”をなぜかすんなりと受け入れ、彼を故郷の星へ帰すために協力する。著者はこの映画を「名作ではないが、なぜか忘れられない作品」と評している。
一般に、物語の構成要素は「人物」「事件」「背景」の3つとされる。『ハワード・ザ・ダック』における「人物」は人語を話すアヒルであり、「事件」は、地球に落ちたこのアヒルがさまざまな困難を乗り越えて故郷の星へ帰ろうとする過程である。「背景」としては、物語の舞台となるアメリカだけでなく、ハワードの故郷の星についても描かれている。
ユヴァル・ノア・ハラリは著書『サピエンス全史』において、「想像と虚構の世界を生み出したことこそが、人類文明発展の第一歩であった」と述べている。前述の3要素は、現実には決して起こり得ない。しかし、想像力を働かせることで、実在しそうな「架空の世界」を創造し、さらに時空間的背景やその他のルールを設定することによって、新たな「世界観」を生み出すことが可能になる。
『ハワード・ザ・ダック』では、“アヒル人間”を存在させるために、架空の惑星「ダックワールド」がつくられた。ダックワールドは、人間のように進化したアヒルが支配する、地球のパラレルワールドとして設定されたのだ。
この映画における物理学的・生物学的な整合性は、さほど重要ではない。それよりも重要なのは、物語としての蓋然性と、「もしかすると実際に存在するかもしれない」と思わせる想像力なのである。
ストーリーと世界観
ビジネスにおけるマーケティング戦略の1つに、「ストーリーテリング」がある。認知心理学者ジェローム・ブルーナーは、「物語を通して情報に接した場合、人はそうでない場合と比べて、情報を22倍記憶しやすくなる」と述べている。
とはいえ、人の記憶力には限界がある。どれほど感銘を受けた作品であっても、時間の経過とともに記憶から薄れていってしまう。そのため、人々が関心を持ち続けてくれるような物語や商品を生み出すには、何らかの仕掛けが必要となる。そして、その仕掛けこそが「世界観」であることに、いち早く気づいたのがビジネス業界の人々であった。