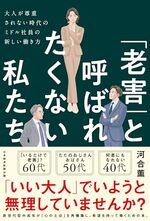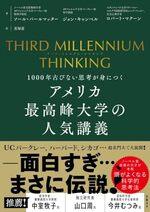人はなぜ、不安に苦しむのか
現代人が不安を抱える理由
人類が不安に苦しみ出したのは、共同体の崩壊が始まった頃からである。長い歴史を振り返ると、共同体を中心としていた頃は、そこに所属していれば自分の存在に意味や価値があるとされた。そこから機能集団へと変わっていき、現代は消費社会、競争社会になった。求められる役割を果たさないと必要とされなくなり、不安が増幅されていく。
そうした消費社会で、誰もが簡単に生きられる方法が売られ、みなそれを買おうとしている。これは、お酒を飲んで寝てしまえば、忘れていられるという消極的解決である。しかし、酔いがさめたときの現実は何も変わっていない。こうした消費社会に生きていると、成長の機会が得られず、人間は不安になってしまう。真に心から触れ合える人とは、自分が成長しないと出会えない。人は他人との関わり合いができてはじめて心の支えが生まれる。ところがいまは、拠りどころがない時代である。一番の問題は信じられるものがないことなのだ。
「現実的な不安」と「神経症的不安」

不安には、現実的な不安と神経症的不安の二つがある。この二つは分けて考えないといけない。精神科医のフロイトは現実的な不安を「客観的不安」と呼び、心理学者のロロ・メイは、これを「正常な不安」と呼ぶ。具体的に対処することで解消できる不安である。
一方で、現実には怖くないものに怯える神経症的不安は、心の内面の問題である。怖くないものを怖いと思い込んでいるため、なぜ自分がそういう性格になってしまったのかを考えなければならない。「周りの人が自分のことを臆病と思うのではないか?」などと思い込み、無理に勇敢に見える行動をとるのは、神経症的不安を持つ人である。