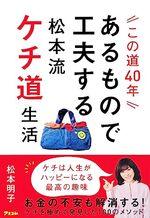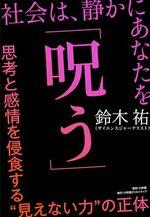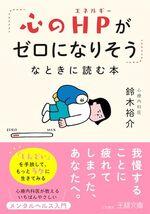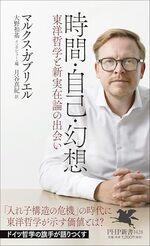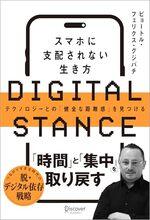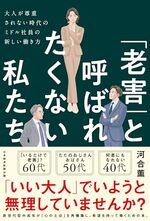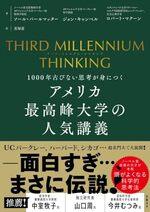【必読ポイント!】 怒り
怒りは武器にもシグナルにもなる
なぜ人には「怒り」という感情が備わっているのか。著者はその理由のひとつに、自分を守る役割があると考えている。
怒りを示すことで敵を遠ざけ、場合によっては相手に余裕や強さを印象づけられる。近頃話題の「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」のように、怒りによって相手をコントロールできるケースもあるだろう。怒りは武器や交渉の手段として活用できるのだ。
怒りをぶつけられる側もこの仕組みを理解しておく必要がある。「この人は今、こうして私を従わせようとしているのだ」という視点をもてば、「相手の攻撃をわざわざ受け止める必要はない」と冷静に考えられるし、自分も感情を武器として使い返す余地が生まれる。
そもそも怒りをもつこと自体は決して悪ではない。しかし、社会の中で生きる以上、怒りという感情はトラブルを招くことが多い。余計な衝突や損失を避けるためには、怒りをどう使うかに自覚的であるべきだ。
「べき思考」が生むイライラ

しんどいときや余裕のないときは、過敏になり、普段よりもイライラしやすくなる。最近やたらイライラするようになったと感じたなら、「自分の調子が悪いのではないか」と考えるきっかけにしてもよいだろう。
さらに、人は年齢を重ねるにつれ、自分の中に「こうするのが常識だろう」「普通はこんなことしないだろう」といった「常識」や「普通」が増えていく。
自分が勝手に作り上げた「こうあるべき」を、心理学では「べき思考」と呼ぶ。この「べき思考」を自分や他人に押しつけた結果、思いどおりにならずイライラや怒りが生まれるケースは少なくない。
上司(または部下)はこうあるべき。メールを受け取ったらすぐに返事をするべき。電車の中では静かにするべき……。こうした「べき思考」の押しつけが通らなかったとき、つまり理想と現実のギャップがイライラや怒りを生むのである。