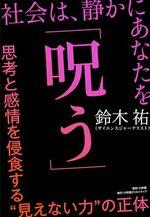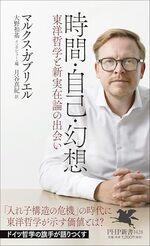江戸文芸のはなし
江戸文化のプロデューサー 蔦屋重三郎

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、江戸時代後期の出版業者である蔦屋重三郎の人生が描かれる。学校の授業ではあまり扱われない江戸文芸のとっかかりにぴったりなのが、蔦屋重三郎だと谷頭氏は言う。
蔦屋重三郎は今でいうプロデューサーだ。浮世絵や読本、狂歌といったジャンルの「キーパーソン」を押さえ、クオリティの高い売れる作品をどんどん作っていった。「この人が言うんだったら」と言うポジションの人を見つけ、その人と関係を築き、自分の活動を広げていった蔦屋の戦略は、現代にも通ずるものだ。
勢力を拡大したあと、蔦屋は自分の版元で若い人を発掘し、江戸時代の大ベストセラー作家たちを育てていく。時代の文化シーンを作っていった蔦屋は、「プロデューサー」と呼ぶにふさわしい人物だ。
三宅氏は、蔦屋のビジネスは現代のDMM的ではないかと指摘する。出版業は最初の資金を生み出せない時期がある。そこで蔦屋は春画や歌舞伎スターのブロマイドを売り出すことで、出版部門の初期資金を生み出し、ベストセラーを産んでいる。現代の出版社が新たな文化シーンを作るための資金を、アイドルの写真集を売ることで作っているのと似た構図だ。蔦屋はプロデューサーであり、経営者でもあったのだ。
谷頭氏も三宅氏の指摘に同意しながら、文化にかけるコストを賄うために別の商売で売上を確保する、こうしたやりくりに江戸文化の豊かさを感じると付け加えた。
コンプライアンス的にアウト!? 『東海道中膝栗毛』
谷頭氏が江戸文芸としておすすめするのは十返舎一九の『東海道中膝栗毛』だ。当時の文学には、江戸時代の一般大衆である「町人」が登場する「町人文学」というジャンルがあった。その代表的な作品が『東海道中膝栗毛』だ。
主人公の「弥次さん」と「喜多さん」は、江戸から伊勢神宮までの「お伊勢参り」の旅をする。東海道の各宿場町を舞台に、一つずつのエピソードが連なっていく、アンソロジー的な性格を持っている作品だ。
内容としてはこの場にはかけないような下世話なネタやコンプライアンス的に完全アウトな話が多いと谷頭氏と三宅氏は口をそろえる。谷頭氏がこうした古典文学で重要だと考えるのは、今ではコンプライアンス的に制限を受けるであろう表現を読み、「人間の生々しさ」について話せる空間が生まれることだ。古典文学は、現代とは異なる言葉で書かれているからこそ、ある程度の距離を持つことができる。そうしたもので、「生々しさ」に触れることは、文学を読む際に欠かせないものでもある。
【必読ポイント!】 物語のはなし
少女漫画の原型がここに 『伊勢物語』
平安の文学で三宅氏がおすすめしたいのは『伊勢物語』だ。俵万智さんの『恋する伊勢物語』(筑摩書房)をきっかけに『伊勢物語』に触れ、『伊勢物語』の原文・現代語訳も読んで、作品自体も好きになった。三宅氏いわく、ここには少女漫画の原型が全部詰まっている。