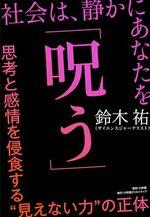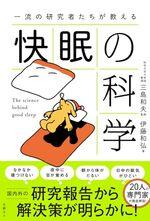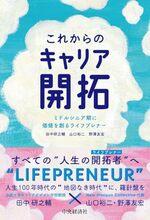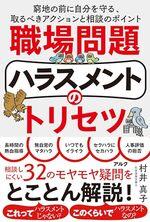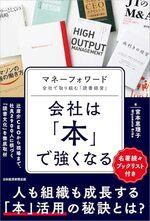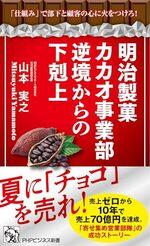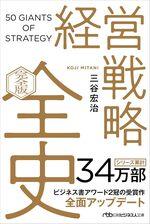若者は本当に怖いのか?──「飲み会嫌い」説の検証
なぜ若者が怖いのか
人材不足が叫ばれる現代において、若者は「希少財」として扱われるようになった。その一方で、オトナ世代は若者を怖がっている。われわれはいったい何に怯えているのか。そして、どうすればその恐れを手放せるのか。
子どもの頃、お化けを怖がっていた私たちは、やがてお化けは存在しないと理解するようになる。また、犬に咬まれるかもしれないと思うと怖いが、正しい接し方を知れば恐怖はやわらぐものだ。
若者に抱く恐怖は、お化けや犬に対する恐怖に似ている。そもそもあなたが怖がっている若者なんて存在しないかもしれないし、全員が常に咬んでくるわけでもない。
恐怖症を克服する手段のひとつは「理解すること」である。とはいえ「正しく理解する」のはとても難しい。
若者は本当に「飲み会嫌い」なのか

若者恐怖症の一因とされるのが、「若者は飲み会嫌い」というイメージである。
メディアやSNSでは、若者が職場の飲み会を嫌っているかのような発信が目立つ。一方で、ある研修講師が2024年に実施した研修の現場では、どの会場でも6〜7割が「上司と飲みに行ってみたい」と答えた。
さらに、日本生産性本部の調査では、2016~18年の3年間、「友人よりも職場の飲み会を優先したい」と答える新卒社会人が80%以上にのぼった。00~15年のあいだは60%程度で推移していたため、最近の若者が「飲み会離れ」しているとは言えそうにない。
その背景を語る要素として、コロナ禍は不可欠だ。コロナ世代に入学した大学生は飲み会文化を経験しづらかったうえ、当時の居酒屋は「社会の敵」として批判された。若者が飲み会離れしているとすれば、それは社会構造の影響による側面が大きいと言える。
「若者が変わった」と怖がる前に、こうした背景事情を想像するべきである。
結論:若手を飲み会に誘っていいのか
若者を飲み会に誘いたくても、「嫌がられそう」「ハラスメントになるのでは」という不安を持つ人は多い。しかし、若者の「飲み会嫌い」には根拠がないのだから、ほかの社員と同様に接したらいいのではないだろうか。ただし、飲み会に慣れていない可能性があるので、配慮は必要だ。
また、ジェンダーギャップやセクハラへの注意も欠かせない。飲み会の目的がコミュニケーションであるなら、代替手段が他にあることは忘れてはいけないだろう。ジェンダーを問わず参加しやすい環境を整え、セクハラに注意を払うべきだ。
飲み会がインフォーマルコミュニケーションの場であり、繰り返し行われる以上、出席者と欠席者のあいだに情報や信頼の格差が生じる。結果として、仕事の成果や昇進にも影響しうるだろう。
だからこそ、若者からの「行かないと損しますか?」という問いには、会社としての答えを準備しておく必要がある。一般論を語るよりも、組織としての立場を明確に示したり、自分の考えを率直に伝えたりすることの方が重要だ。