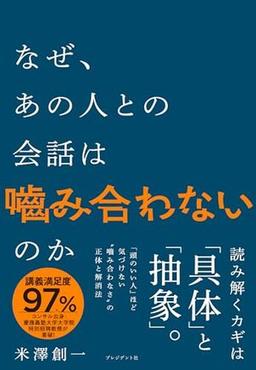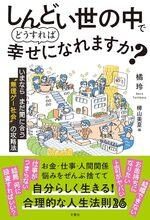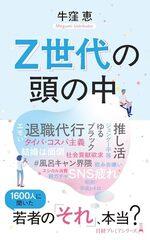なぜ、会話が嚙み合わないのか
「思考スタイル」の違い
質問にきちんと答えてくれない。概要だけでいいのに詳細ばかり話してくる。主旨から外れたどうでもいいような質問ばかりする――。こんな「嚙み合わない会話」に困った経験はないだろうか。
会話が嚙み合わないのは、各人の「具体」「抽象」のレベルと、その組み合わせによる「思考スタイル」の違いを意識していないことから生じる。例えば、個別の課題を相談したい部下に対し、抽象的な理念ばかりを語る上司。家事分担を決めたい妻に対し、一部だけを手伝って「やってるつもり」になっている夫。これらはすべて、相手の思考スタイルを意識しないから起きるのだ。
コミュニケーションの齟齬を減らすためには、自分と相手の思考スタイルを知り、その違いを踏まえた伝え方をしていく必要がある。相手の思考スタイルを理解できれば、周りの「困った人」とのコミュニケーションも改善されていくはずだ。
本書では、「具体的知識(具体)」と「抽象化能力(抽象)」の両面から思考スタイルを可視化し、コミュニケーションの改善法を提案していく。
「思考スタイル」を構成するもの
「具体的知識」と「抽象化能力」

「具体的知識」とは、文字通り、対象についての具体的な知識や情報だ。対象についてどれだけ詳しいか、その経験や情報をどれだけ持っているかである。
一方、「抽象化能力」とは、具体的な事象や経験から共通点や本質的な特徴を見出し、より一般的な概念や原理として理解し、表現する能力だ。個別の話をまとめたり、応用したりする力を指す。
具体的知識と抽象化能力は相互補完関係にあり、どちらが欠けても十分な思考力が発揮できない。具体と抽象は二項対立ではなく、バランスよく向上させることが重要だ。
「具体的知識」のレベル
具体的知識と抽象化能力には、それぞれ成長段階としてのレベルがある。
具体的知識のレベルは、ある対象をどれだけ正確に詳細に把握しているかという解像度と、どこまでの範囲で把握しているかという視野で決まる。レベルは0から4まで、以下のようにわけられる。
レベル0 低次元(霧の中):解像度が低く、視野の認識がない。事実誤認や断片的な把握に留まる。