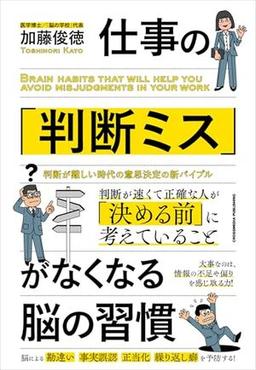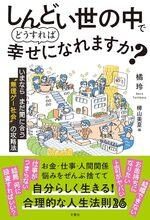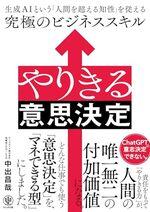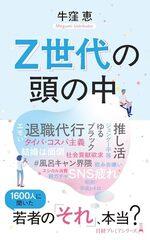なぜ人は判断ミスをするのか
判断の4段階とその落とし穴

私たちは物事を判断する際、次の4段階を経ていると考えられる。
(1)知覚・認知の段階
(2)感情・欲望の段階
(3)理解・記憶・分析の段階
(4)判断・選択・実行の段階
それぞれを具体的に見ていこう。
例えば、友人の家を訪れたあなたは「先に部屋に入って待っていてほしい」と言われたとする。部屋に入ると机の上にバナナが置いてあった。まず視覚を通じてその存在を認識する。しかし、それは精巧なサンプルかもしれない。手に取って匂いを嗅ぎ、確かに本物だと知覚する(知覚・認知)。
本物だとわかると、ちょうど空腹だったあなたは食べたいという気持ちを抱く(感情・欲望)。だが、そのバナナは友人のものであり、勝手に食べればまずいことになると理解する(理解・記憶・分析)。とはいえ友人から「部屋で自由にくつろいでいていいよ」と言われたことを思い出し、きっと自分のために用意されたものだろうと考えて食べてしまった(判断・選択・実行)。
このように、バナナを認知してから食べるまでには4つの段階がある。そしてそれぞれに判断ミスの要因が潜んでいる。
「知覚・認知」の段階では、視覚だけに頼ればサンプルを食べてしまう危険があった。これは五感情報の不足による判断ミスだ。正しい判断のためには客観的で多角的な情報収集が必要だといえる。
次の「感情・欲望」の段階では、空腹ゆえに「食べたい」と思ってしまった。実際に食べて友人を怒らせたなら、それは感情・欲望に流された結果の判断ミスである。
さらに「理解・記憶・分析」と「判断・選択・実行」の段階では、「自由にくつろいでいいよ」という言葉を拡大解釈した。友人にその意図がなければ、それは思考のバイアスによる曲解だ。本人が理性的に結論を導いたつもりでも、無意識のバイアスが判断を狂わせることになる。
思考のノイズと判断ミス
ここでは、判断ミスを招く「思考のノイズ」について取り上げたい。
例えば、上司から「1週間後にレポートを提出せよ」と命じられたとしよう。思考のノイズが少ない人は、まず「レポートの狙いと目的」「レポートの内容の構成」「レポートの大体の分量」といった必要最低限のチェックポイントを上司に確認する。そのうえで提出期限から逆算し、大まかな日程を立てて作業に着手するだろう。余計なことに注意を奪われず、集中して作成に取り組み、期限に間に合わせる。
一方、思考のノイズが多い人はチェックポイントに集中できない。「なぜこの時期に自分が任されたのか」「上司の表情が硬かったのは何か理由があるのか」といった、本来考える必要のないことに心をとらわれてしまうのだ。結果として、判断ミスをしやすくなる。