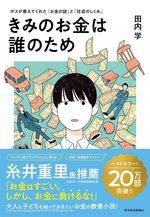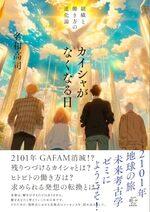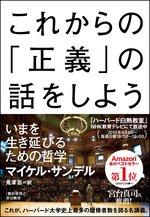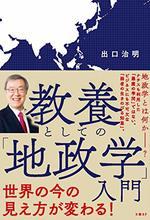ミクロ経済学とマクロ経済学
経済学とは何か

経済学とは、「さまざまな人や組織(=経済主体。家計、企業、政府など)が市場でモノ(=財、サービス)やお金を交換しあう活動(=経済活動)を、ある仮説をもとにモデル化し、シンプルかつ理論的に説明しようとする学問」である。ここにおいて、経済主体すなわち人間は、「ある経済的な目的を達成するために、与えられた制約の中でもっとも望ましい行為を選択する行動(=最適化行動)」をとる、と想定する。すなわち、経済学は「制約付きの最大化問題を用いて分析する学問」なのである。
経済学には大きく分けて2つの専門分野がある。ミクロ経済学とマクロ経済学だ。前者は1つひとつの家計など個別の経済主体の行動分析から、「市場全体の需要と供給の分析を積み上げて経済を説明」する。後者のマクロ経済学は、「物価、インフレーションや失業、国民総生産の決定、経済成長など国民経済全体の経済の動き」に着目する。ミクロとマクロは互いに補い合う存在であり、マクロ的な分析でも、個々の経済主体による最適化行動を前提とするミクロ的な基礎が重要となる。
また経済学では、「社会的な必要性の高さ」を示す希少性の考え方が大事だ。希少性は相対的な需要と供給の関係性によって決まる。砂漠で道に迷って喉がカラカラな状態なら、1万円を出してでも水を買いたいと考えるかもしれない。
ある財の需要の増加は価格の上昇を招き、企業の市場参入のインセンティブになって、結果としてその財の供給も増える。これには費用(コスト)の考え方も関わってくる。需要が高いならコストをかけてでもその財を生産しようとするだろう。費用は「何らかの経済行為をする際にかかる損失」だ。家計にとっての購入金額、企業にとっての賃金や利子は、費用となる。他のことに資金を回したことであきらめたことになる収入、機会費用の考え方も重要だ。
以下では、ミクロ経済学の必須テーマを中心として、マクロ経済学はその概要のみを紹介する。
【必読ポイント!】 ミクロ経済学の基本
限界
「モノの値段は需要と供給の相対的な関係で決まる」が、この需要と供給の量も価格変化の影響を受ける。
家計がリンゴを買おうとするとき、その1個あたりの価格が、いわゆる財1単位あたりのコストとなる。これは消費者の購入する数と独立に決まっているようにみえるので、「市場価格は購入量とは独立の一定値を取る」と経済学的には表現できる。家計は、何個のリンゴを買うと自分たちにとってもっとも得になるか、意思決定することになる。
そこで必要となるのが、増加分をあらわす「限界」の概念だ。100円のリンゴをすでに3個購入していた場合、もう1つリンゴを追加購入するときの限界購入金額は、「1単位だけ余計にその財を購入するときにかかる総コストの増加分(=限界コスト)」としてあらわせる。このとき、「価格はその財を消費する際の限界コストの指標」となる。
また、リンゴ2個より3個を買うほうが満足度(効用)の総量は上がるものの、リンゴ1個を買うことで得られる満足度は下がっていく。「財をひとつ買うことで得られる満足度を金銭的な大きさに置き直したもの」を限界メリットという。