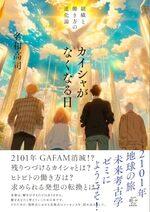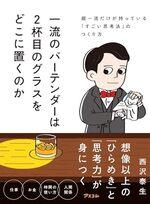1 / 2
『論語』と「学び」の本質
発憤――『論語』と「自己啓発」

自己啓発の「啓発」という語と『論語』とのあいだには、深い結びつきがある。実際の引用を見てみよう。
[書き下し文]
子(し)の曰わく、憤(ふん)せずんば啓(けい)せず。悱(ひ)せずんば発(はっ)せず。一隅(いちぐう)を挙(あ)げてこれに示(しめ)し、三隅(さんぐう)を以(もっ)て反(か)えらざれば、則(すなわ)ち復(ま)たせざるなり。
[現代語訳]
先生がいわれた、「〔わかりそうでわからず、〕わくわくしているのでなければ、指導しない。〔言えそうで言えず、〕口をもぐもぐさせているのでなければ、はっきり教えない。一つの隅をとりあげて示すとあとの三つの隅で答えるというほどでないと、くりかえすことをしない。」
原文はこのようになっている。
「不憤不啓(ふふんふけい) 不悱不発(ふひふはつ)」
自己啓発の「啓発」は、じつはこの章句の2字を取って生まれた語である。したがって、「学びの本質」に迫るためには、「啓」と「発」だけでなく、「憤」と「悱」をセットにして理解する過程が欠かせない。