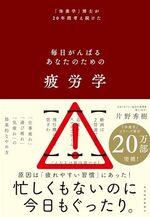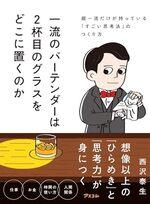【必読ポイント!】 技術解説編
話が面白いという最強のスキルについて
著者の好きな物語に『千夜一夜物語』がある。妻に浮気されて以来女性不信になったペルシャの王は、若い娘を毎夜寝床に呼んでは首を刎ねるという残虐の限りを尽くしていた。ある晩に呼ばれたシェヘラザードは、自分の知る物語を王に語る。そのあまりの面白さに、王は続きをせがみ、シェヘラザードは毎夜寝床で話をし続けた。千夜が明けたころ、王は彼女を正妻に迎え、暴虐は止められていた。
この話を大学生のころに読んだ著者は、財産も地位も力もない、弱い立場の人であっても話の面白さで自分の身を助けることができるということに感動した。「話が面白い」とは、最強の技術だ。それを実現するのは、インプットした内容を、面白く語ることができるようになることだ。
「①話を仕込む」「②話を解釈する」「③話すときに②を使う」という3つのプロセスをたくさん踏んだ人は、話が面白くなっている。これが無意識にできる人もいるが、意識的にやったほうがその効果は高くなるはずだ。
味わった作品を上手く「料理」してネタにする

何かを読んだとき、それを「ネタ」にするためには、具体的には①〈比較〉ほかの作品と比べる、②〈抽象〉テーマを言葉にする、③〈発見〉書かれていないものを見つける、というプロセスが必要となる。この3つができるようになると、応用として④〈流行〉時代の共通点として語る、⑤〈不易〉普遍的なテーマとして語る、ということも可能になる。
観たものや読んだものに対して、この5つのどれかの鑑賞・解釈ができるようになると、人に話すことができる状態になる。