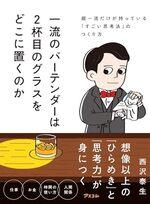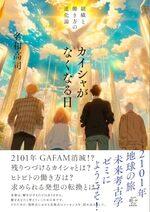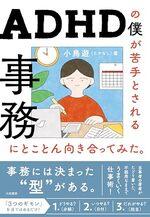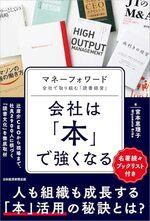正解を求める
批評から考察へ

「考察」という言葉は最近、新しい文脈のなかで使われている。「事件の真犯人などの『謎』を、作中のヒントから推察し、その推察をSNSやブログで語ること」を指す。しかも「考察」文化はドラマに限ったものでもない。ミステリのジャンルではない作品であっても、「作者は謎を仕掛けている」という前提で、視聴者や読者みずから考察する。それが、現代の「フィクション受容になりつつある」のだ。
2024年には映画化もされたウェブライター雨穴による小説『変な家』は、この傾向を小説で実現した「考察小説」である。知人から手渡されたとある家の間取りから謎を読み解いていくこの作品では、間取りに存在する違和感を「考察」せよと作者みずから伝えてくる。それまでのミステリ小説であれば、ひとつの「謎」以外にも人間関係や関連する事件の詳細などが語られる。しかし『変な家』の前半では、人間の感情などを排除して間取りの謎の提示に終始している。考察小説はこのように、読者による考察と「一つだけの正解」を知るプロセスが用意されているのだ。
この考察の時代では、『鬼滅の刃』や『ONE PIECE』などの作品でも、「伏線回収」「裏設定」などの字がタイトルに躍る考察動画が多い。制作者たちが仕掛けたであろう「気づかれていない」真実を伝えようとする。考察文化は作品の受容体験自体を「正解のあるゲーム」に変えているといえよう。
こうした「考察」がない時代は、「批評の時代」であった。ここでの批評は、「作者すら思いついていない作品の解釈を提示する」ことである。考察には、「作者の意図」への意識がある。
NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』では、2023年公開の映画『君たちはどう生きるか』について、「宮﨑駿が高畑勲の死を乗り越えるためだけにつくった、自分たちの関係性をアニメに映し出した作品」という「ジブリからの回答」があるかのように紹介されていた。この映像を観た人は、制作者による“答え”を知ったと思って、安心するに違いない。しかし、『君たちはどう生きるか』ではたとえば、主人公の少年が抱く葛藤が克明に描かれており、それを宮﨑駿と高畑勲の関係において読み解くのはなかなか難しい。こうした複雑さは、「考察の時代」には好まれないのである。