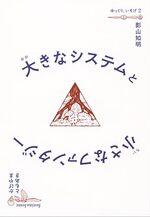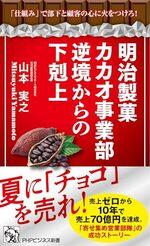【必読ポイント!】 本づくりは最高だ
楽しくて味わい深い

「つくり手の『want』を詰め込んだ本」が「自分のためにつくる本」である。マーケットのことは考えず、自由な発想で、自分の「好き」を詰め込み、既存の出版流通に乗らない。
出版社は読者のために本をつくる。著者や編集者をはじめ、出版社は「社会的意義がある」という信念にもとづいて前へと進んでいく。一方「自分のためにつくる本」は読者も社会も見てはいない。「自分の哲学や思想、世界観をピュアに表現し尽くすのみ」である。だから、個性溢れる、誰にも忖度しなくていい、ユニークな本が生まれる。タイトルや内容だけでなく、大量生産には向かない仕立ての本でも、「自分に刺さればそれでいい」。
『ハトは否定形に飛ぶ』という詩集は、「本をつくりたいという夢をいつまでも夢のままにしておきたくない」との強い思いがかたちとなったものだ。出版社との仕事では「『わたし』が薄まる」と感じ、藤原印刷に足を運んだ。紙選びへのこだわりが強く、何度も打ち合わせを重ね、紙のギャラリーに足を運んでみても、なかなか決まらない。その過程で「わたしらしさ」を定めなおしてみたら、書店でピッタリの印象の紙に心奪われた。その本の印刷会社に問い合わせてみたところ、該当の紙はすでに廃番となっていたが、近い紙を教えてもらえた。コストのかかる特殊な製本も、見本を見ているうちに諦められなくなった。松本にある藤原印刷の工場まで足を運び、印刷の立ち会いも体験した。そうして作者という一個人がすべて詰め込まれた本は、まさに「本づくりの魅力が詰まった本」であった。
「自分のためにつくる本」は、利益も原価率も考えなくていい。「自分がお財布から出せる額」をそのまま制作費にかけられる。だから、理想とする仕様を心ゆくまで選んでも問題ない。予算内で納得できるかたちにおさめていくことも、自分らしさの表現のひとつだ。そこにも「本づくりのおもしろさ」がある。
人を惹きつける本
個人のつくり手のほとんどは、ベストセラーを目指してはいない。利益ではなく「自分が納得するか」が優先される。そんななかから、「思いがけず売れていく」本があらわれることもある。