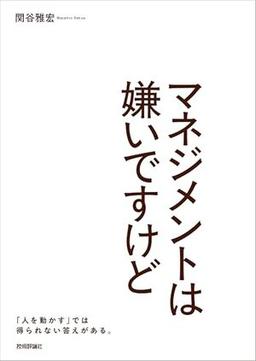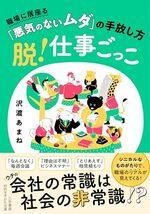マネージャーになってしまった!
自分自身の心の持ち方
マネージャーとして組織を率いるときに大事になるのは「自分自身の心の持ち方」だ。「こうあってほしい」という理想を当てはめるのではなく、まず目の前の現実を受け入れ、今後どうしていくかを考える必要がある。
著者は「うまくいくかどうかは半々の確率」「仕事は頼んだほうにも責任がある」「ないものを作るのだから、失敗しても今より悪くはならない」「自分がマネージャーを任されたのは実績があるからではない」と考えるようにした。こう考えることで、「自分自身」と「マネージャーという役割」を切り離せるからだ。
成果とスキルアップの両立問題

マネージャーになった著者が最初に取り組んだのは、技術者個人のスキルアップと、業務のアウトプットの両立である。著者の組織の業務は「技術サポート」であったため、アウトプットは「他部門の問題を解決すること」となる。
しかし当然ながら、技術者の能力は均一ではない。こういった場合に組織がやりがちなのは、能力の高いメンバーにフル回転で働いてもらい、成果を上げることだ。
だがこれには問題がある。まず、仕事が能力の高い人たちに集中してしまうこと。そして担当者個人の技術力によって、組織として請け負うサービスの質にバラツキが出ることだ。すると、仕事が人に固定される「属人化」が起き、チーム内に非協力的なムードが漂ってしまう。
著者はそれを避けるべく、次の3つを組織の核に置くことにした。
・アウトプットは組織の時間で換算する
・目指すのは「アウトプットの最大化」ではなく「安定的なアウトプット」
・「技術者を養成すること」を仕事の中に組み込む
次項ではこれらを実現するためにおこなったことを紹介する。
学びの余力を残しておく
通常、アウトプットには最大限の力で取り組むことが期待される。しかし、それでは個人も組織も消耗してしまい、学びや成長にリソースを割くことができない。