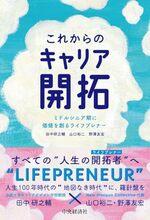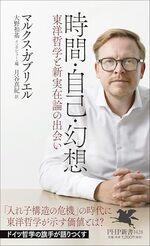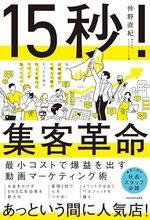孤立社会は誰がつくったのか?
幸せに法則性を見出す
幸福な人や集団の実態は多様である。だからこそ、統一的な法則が見出せれば、人生や社会を大きく変えられる。
これまでは幸せな状態かどうかの調査方法が限られていた。そこで著者らは、独自のウェアラブルセンサや、人間行動をより多角的に映し出す計測機器を開発し、膨大な定量データを集めた。また、個人が感じる「幸せ」「孤独」などの心理要因を調べた定性データも加え、総合的な分析を行った。その結果浮かび上がった、幸せや生産性を左右する決定的な要素「ファクターX」について述べていく。
コミュニケーション量は孤立感と関係ない
現在、孤立感の広がりは社会の病といえるほど深刻な影響をもたらしている。孤立を感じる人は、うつ傾向やうつ病に陥りやすい。孤立感は周囲にも広がり、生産性や創造性の低下を招くうえに、身体的な健康リスクを高めることが知られている。
重要なのは、孤立感は主観的な現象ということだ。周りにたくさん人がいて会話が多いことと、孤立を感じることは別物である。現に、つながりの数やコミュニケーションの時間が多い人たちと少ない人たちの孤立感の数値に有意な差は見られなかった。
孤立を感じる人の周囲にはV字が多い

孤立感を抱きやすい人には、人間関係の「形」に特徴がある。あなたと会話する相手を2人選んだとき、AさんとBさんが互いに会話をしない関係なら「V字」、会話をする関係なら「三角形」となる。著者らの解析によれば、周囲にV字が多い人は孤立感を抱きやすく、三角形が多い人は抱きにくい。つまり、V字と三角形のどちらがその人の周りに多いかが、孤立感を左右するのだ。