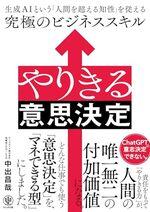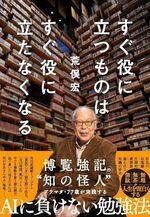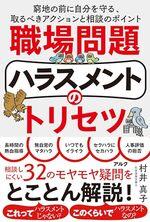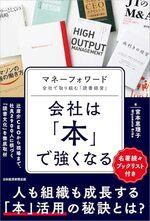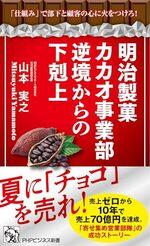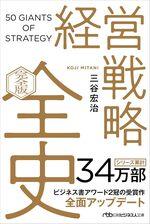フィードバックとは何か
「ティーチング」と「コーチング」の二項対立を超える
日本の職場で管理職が部下を導く際、かつて主役だったのは「どう教えるか」「どう指示するか」「どう伝えるか」であった。上下のヒエラルキーに沿う一方通行の情報伝達が善とされ、現場の実務においても会議や面談の作法においても、その価値観が色濃く反映されていた。要するに、部下育成は長いあいだティーチング(教えること)が主流だったのだ。
やがて2000年代後半、舞台に躍り出たのがコーチングである。端的に言えば「他者の目的達成を支援する技術」だ。一方向の部下育成法が当たり前だった現場で、当人の内省と自律を引き出す手法として注目を浴び、次第に存在感を増していった。各社の現場に、制度や会話の型として導入されていったのである。
この潮流自体は健全だが、当時の導入・紹介の文脈には誤解が少なくなかった。コーチングはしばしばティーチングの仮想敵とされ、「コーチングこそが正解で、ティーチングは時代遅れだ」と高らかに謳われたのである。その結果、現場ではティーチングがことさらに否定され、コーチング一色へと染まっていった。
しかし、白黒の構図が機能しないことは、少し考えれば誰でもわかる。育成にはティーチングが有効な場面もあれば、コーチングがふさわしい局面もある。つまり「ケースバイケース」なのである。
フィードバックの2つの要素

では、どうしたらいいのか。そこで注目されるのが、両者を包括する上位の枠組み――フィードバックである。「相手に気づかせるのか、それとも教えるのか」といった二項対立から脱し、双方のバランスを取りながら部下を育成するのである。
フィードバックの定義はさまざま存在するが、本書では次の2つの要素から成立するものとする。