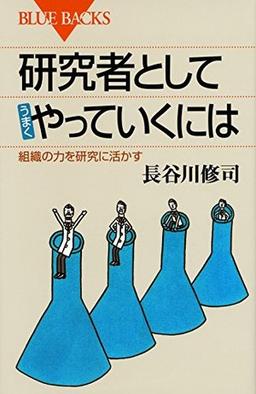【必読ポイント!】 「研究者」という職業
「研究」と「勉強」はまったく違う

大学院は実際に研究を始める場所として最も身近な場所だが、「大学院で何をやるのか」を正しくイメージできる人は少ない。「たくさん知識を身につけ、『博識』になること」だと漠然と想像する人も多いだろうが、実際にはまったく違う。大学院は「勉強」するところではなく、「研究」するところなのである。
勉強とは答えのわかっている問題や課題を考え、先人たちがすでに考えた課題や解いた問題をもう一度自分でやってみて、知識体系を学ぶことだ。これに対して研究とは、答えのわかっていない課題を考えることである。ときには答えがあるのかどうかさえわかっていない課題、あるいは考える意味があるのかどうかさえわからない課題さえも考えなければならない。価値ある謎や課題を見つけること自体が、研究の大きな部分を占めているのだ。
研究の結果、意味のある成果が得られたら、それが学問体系の中に組みこまれて蓄積されていく。そしてその知識体系を大学生が「勉強」するというわけである。研究とは、その知識体系の「最前線の先」を探っていく営みだといえよう。
研究は非効率的なもの
学部までの勉強のやり方をむやみに続けていても、創造的なものは生みだせない。自分の研究に合わせて、既知の知識を今までにないやり方で組みあわせることが、独創性を生みだすことにつながる。
とはいえ、自分の研究に関連する分野の知識を全部勉強したあとでないと、新発見するための研究ができないというわけではない。とりあえずはあまり大きな心配をせずに、自分の研究に関係する狭い範囲の勉強だけして、研究をどんどん進めたほうがいい。
また、自分と同様の研究を過去に誰かがやっていたとしても、同じ結論にならないこともある。先行研究にあまりとらわれずに、自分のアイディアにもとづいて、やってみることが重要だ。
断片的で系統的でない発見や発明の積み重ねによって、科学や技術、学問は発展していく。研究とは基本的に非効率的なものなのである。
研究は自己表現
研究者の日常は、ほとんど毎日、研究がうまくいかなくて悶々と悩むことばかりだ。研究費の申請書を書いたり、研究の報告書を書いたりと、けっして楽しいとはいえない仕事も多い。
しかし、研究者の多くは飽きもせず、毎日黙々と自分の研究に向かいあっている。新しいことを発見したり、自作の装置がうまく働いたりしたときの嬉しさは格別だからだ。
研究者の個性や価値観によって、研究成果や研究スタイルは大きく異なる。芸術家は自分の作った作品によって自己表現をするが、ある意味で研究者は自分のやった研究によって自己表現をするともいえる。研究は、自分らしさの表現でもあるのだ。
研究者への助走
教養はあとから効いてくる

大学1、2年生では、まだ専門教育が本格的に始まらない大学が多い。しかし、教育課程のときこそ、たとえ自分の進むべき専門分野が決まっていたとしても、幅広い分野の本を読んだり、講演会に出てみたりすることをお薦めしたい。
研究者は、「井の中の蛙」あるいは「たこつぼ」状態になってしまうことが多い職業である。もちろん、特定の専門分野の最先端を研究するには、深い「井の中」に潜ってひとつの研究テーマに集中するべきだ。しかし、ときどき「井の中」から這いでて、周りを見わたす心の余裕と見識を持っておくべきである。
大学前期の教養課程での勉強は、その素養を身につけるきっかけになる。教養とは、自分の専門や考え方を相対化できる能力なのである。
博士は修士の延長ではない
大学院では必修の講義の数は少ないため、ほとんどの時間を研究に費やすのが常だ。学部生とは違い、研究の準備からすべて自分でやらなければならないため、より主体的な活動が求められることになる。
とくに、