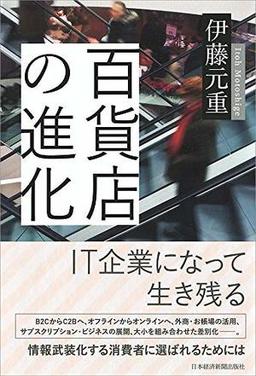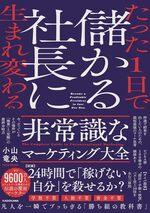減少する売り上げ
バブル崩壊後、百貨店の売り上げが減少
百貨店の売上高が顕著な形で減少を始めたのは、1990年前後のバブル崩壊の頃からだ。91年まで順調に拡大を続けてきたが、同年の9兆7131億円をピークに減少を続けている。2016年には5兆9780億円にまで減少。25年間で約38%縮小したことになる。
一方、コンビニエンスストアやドラッグストアは売上高を伸ばしている。小売り全体の売上高に大きな変化はない。そんな中、百貨店の売上高が落ちており、シェアも縮小の一途をたどっている。
様々な業態の成長が招いた「百貨店の地位低下」
様々な形態の小売業が生まれてくることで、小売業全体の中で百貨店がカバーする領域が相対的に狭まってきている。
具体的には、ロードサイド店から始まった紳士服専門店や、ユニクロ、ニトリなどのSPA(自社で商品開発する小売業)の躍進、地方都市を中心とする大型モールの広がりなどがあげられる。さらに都市部では、コンビニの成長が著しいことに加え、JR各社による駅周辺の商業施設整備なども、影響力が大きい。こうした結果として、百貨店のシェアが削られているのだ。
衣料品の凋落

百貨店の売り上げ減少のもう一つの要因は何か。それは、多様な商品を大量に販売する「マスマーケティング」手法の行き詰まりだ。アパレル、とりわけ婦人服の売り上げ減少は顕著である。
これまで、婦人服は百貨店にとって有利な商品だった。ユニクロのようなファストファッションが出現するまでは、百貨店に対抗できるような強力な専門店が出てこなかった。つまり、価格面や品質で棲み分けができていた。百貨店での婦人服の販売は、アパレルメーカーとの二人三脚で展開してきたといっていい。
しかし、消費者の嗜好が多様化し、百貨店が得意としていた衣料品を売りまくる時代ではなくなった。こうした手法が限界に近づいてきたことが、売上高減少につながっている。
再編が進む百貨店業界
ある時期を境に業界全体の規模が縮小するセクターは珍しくない。その一つが百貨店業界である。2006年以降、百貨店業界では再編が進んでいる。都市型の大手小売業は合併することで競争力の強化を図ってきた。一部の百貨店は経営破綻に陥り、それに近い状態から他のグループ企業の傘下に入る百貨店もあった。地方の百貨店でも淘汰と系列化が起きている。
現在、百貨店業界は、上位の大手数社が大きなシェアを占める寡占的な構造になりつつある。バブル経済崩壊後の日本では、金融業界や家電業界のように再編が進んだセクターは多い。だが、百貨店の現状が最終形になるかどうかは予断を許さない。
【必読ポイント!】 情報武装する消費者と百貨店の関係
情報がばらける時代

百貨店という小売業は、様々な機能の束から構成されている。たとえば、店員からの丁寧な商品説明の機会や、「百貨店の商品であれば品質が保証されている」という安心感、飲食の楽しみの提供などである。
しかし情報化が進展するにつれ、百貨店が提供してきた情報がばらける、すなわち「アンバンドリング」の時代になっている。かつては百貨店に足を運ばなければ得られなかった情報が、今はインターネットで簡単に入手できる。そのうえ、店ごとの価格の違いも知ることができる。消費者が情報で武装する時代において、消費者が百貨店に買い物に行く意味は何だろうか。