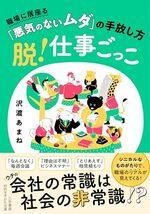決断を下すには事前のルール作りが必要
組織やチームが納得するプロセスを踏む
「どちらを選ぶべきかわからない」「絶対に正しいかわからない」など、答えがない問題は世の中にたくさんある。もちろんビジネスにおいても同様だ。
しかし誰もが決められない問題に関して、「このようにすべきだ」と決断を下して、その責任を取ることがリーダーの役割である。答えがあるかどうかすらわからない問題に対して、「絶対に正しい答え」を求めて、決断を先送りするようではリーダー失格だ。時間が限られるなか、周囲から反発されようとも決断を下し、組織やチームを動かしていくことがリーダーには求められる。
一方で、「この案でいこう」と決めたとき、その案に賛成していない人たちがいることを忘れてはならない。彼らにも最終的には納得してもらう必要がある。組織やチームのメンバーの納得感が低いままに物事を進めてしまうと、途中で頓挫してしまうかもしれない。決断を下すときは、それぞれのメンバーが納得できるような決断プロセスを踏むことが大切なのである。
メンバーが納得できる決断のプロセス「手続的正義」
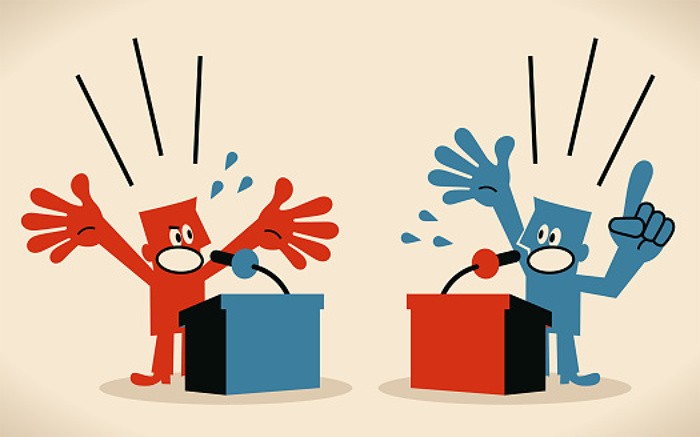
では、どのような決断プロセスを踏めば、メンバーが納得してくれるのだろうか。その答えは「手続的正義」という考え方にある。司法の世界では、「実体的正義」と「手続的正義」という2つの考え方がある。
実体的正義とは、「ある結果の内容自体に正当性があるかどうかを問う考え方」である。つまり「絶対的に正しい結果かどうか」が判断基準だ。
一方で手続的正義とは、「結果に至る過程・プロセスに正当性があるなら、正しい結果とみなす」という考え方だ。つまりここで論点となるのは、「適切な手続きに従って判断された結果かどうか」である。
ケーキを公平に二等分する方法
たとえば、「公平に2人でケーキを2つに分ける」にはどうしたらいいだろうか。ここでは、「2人はお互いに大きいほうを取りたい」と考えていることにする。
「単純にケーキを正確に二等分すればいいのではないか」と思うかもしれない。しかしどんなに高性能な機械を準備しても、正確に二等分することはきわめて難しい。突き詰めていくと、ミリ単位やナノ単位で誤差は生じてしまう。したがってこの方法は現実的ではない。
しかし手続的正義のやり方にもとづいたルール・プロセスを作れば、2人が納得するようにケーキを分けることも可能だ。まず1人がケーキを二等分に切り、次にそのケーキを切らなかった人が好きな方のケーキを選ぶ。そしてケーキを切った人が、残った方のケーキをもらうのである。
こうすれば、切る人は自分が損をしないようにケーキを二等分するだろう。誤差が出て小さい方のケーキをもらうことになっても、自分が切ったので不満は残らない。また、切らなかった人は大きい方を選べるので、もちろん不満は残らない。
このように、厳密に二等分しなくても「双方が納得するルール・プロセスがあればよい」とするのが、手続的正義の考え方である。
多数決の結果を認めさせるには仕組み作りが大切
「このまま事業を継続すべきか」「事業を撤退すべきか」などの問いの答えは誰にもわからない。しかしビジネスの世界において、正しいと思うことのみを追求していては、事業が成り立たなくなってしまう。
ゆえに