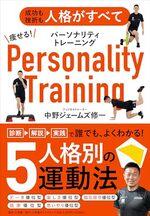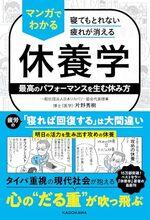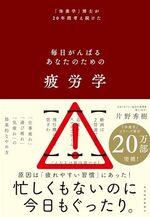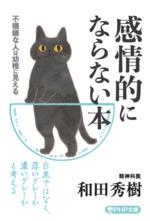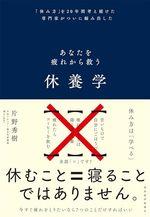【必読ポイント!】 なぜ、登山は健康に良いのか
登山が心身に与える影響
登山と健康の関係について著者が調査した結果によると、中高年から登山を始めた250人あまりの人のうち、プラスの影響があったと回答した人は7割以上であった。病気の改善といった「体力・健康」や「精神面」の項目で多様な好影響がある様子がうかがえる。
一方、1割程度の人はマイナスの影響があったと回答している。その多くは膝と腰の痛みだ。しかし、登山を始めてから膝と腰の痛みが改善したと答えた人も多かったため、登山のやり方次第で良くも悪くもなると考えられる。マイナスの影響に留意して登山すれば、登山は心身の健康増進にとって優れた運動となる。
健康増進のためにウォーキングが推奨されることが多いが、登山はウォーキングよりも心拍数の増加が高く、運動時間が長い。代表的な有酸素運動であるウォーキングよりもさらに効果の高い運動だ。
筋や骨を鍛える効果

有酸素運動である登山には、肺や心臓の能力の改善や、肥満の予防・解消の効果が期待できる。さらに、筋や骨を強化する効果もある。
筋電図を用いて調べると、登山はウォーキングよりもかなり大きな筋力発揮をしている様子が観察できる。骨は、そこに付着している筋が大きな力を発揮するときや、骨自体が衝撃を受けたときなどに硬くなる性質がある。登山の荷物運びの負荷や下り道の衝撃は、骨の強化にも有効だ。
ただし、自分の体力や経験に見合わない強度の登山をいきなり行うと、負荷が高すぎて不健康な運動になってしまう。特に、心臓に疾患がある人は、心疾患を引き起こす可能性もあるため注意が必要だ。筋や骨も同様で、普段から活発な運動をしていない人が準備をせずに登山をすれば、怪我につながりかねない。

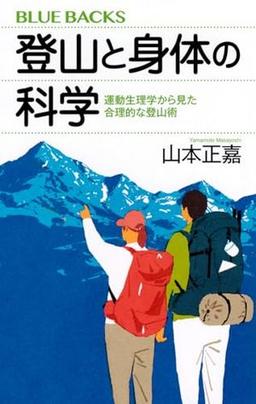



![進化思考[増補改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F3904_cover_150.jpg&w=3840&q=75)