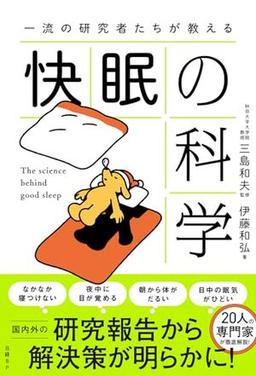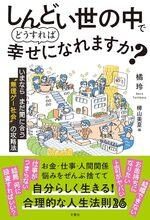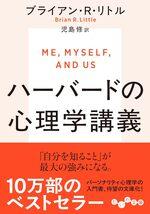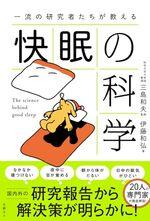【必読ポイント!】 睡眠の「なぜ?」を知る
眠気の正体

ちゃんと寝たつもりなのに感じる眠気。その実体は少しずつ明らかになっている。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構長の柳沢正史教授は、この眠気のメカニズムについて、「日本庭園にある『ししおどし』」にたとえている。ししおどしの筒が上を向いている状態が覚醒、水の重みで倒れた状態が睡眠であり、たまっていく水が眠気というわけだ。蓄積された眠気が一定のレベルを超えると、わずか1秒の間に睡眠へと切り替わる。そこで十分に眠ることができれば、眠気が抜けて覚醒状態に戻る。
「覚醒と睡眠を切り替えるスイッチが脳の中にあること」は最近の研究でわかってきた。しかし、眠気そのものや、スイッチが切り替わるメカニズムについてはまだまだ探究中のテーマだ。
柳沢氏らは、眠気の実体に迫った論文を2018年に「ネイチャー誌」に発表している。先天的な過眠症の変異マウス「スリーピー」は、「特定のたんぱく質にリン酸基をつける『リン酸化酵素』の1つが過剰に働いている状態」であり、そのせいで眠気が解消されないと考えられる。遺伝子変異のないマウスに軽い刺激を与え、眠らせないようにしても、「特定のたんぱく質のリン酸化が進む」状態が見られた。このとき、「睡眠を取ることでたんぱく質のリン酸化が解消された」という。
起きている時間に、脳は外界からの情報をつねに受け取るが、不必要な記憶などもたまっていく。それと同時に、脳のシナプスなどで特定のたんぱく質のリン酸化が進み、眠気となってあらわれる。そうして、「いらない記憶や情報を整理するために、睡眠が促されているのではないか」と考えられている。意識を失い、外界から切り離されたオフラインモードで「メンテナンスをするのが『睡眠』」なのだ。
7時間寝ても「3時間」
「寝つくのに2時間以上かかった」というような入眠障害や、途中で目が覚めて再び眠りにつけなくなる睡眠維持障害などを抱える不眠症の問題に悩む人は少なくない。ただし、それらの基準は主観的なものだ。「客観的な睡眠の状況と主観的な睡眠の状況が異なるケースはとても多い」という。
脳波的には7時間眠っているのに、3時間しか寝ていないように感じる。この状態を「睡眠誤認」と呼ぶ。当人が眠れていないと感じるだけで、精神的な不快さだけでなく、実際に身体的な不調があらわれてしまう。
主観的に感じる不眠症と客観的な不眠は別物のはずだが、臨床現場では同様に扱われることが多い。そもそも、「『睡眠を客観的に測る』ということに対するハードルが非常に高い」からだ。