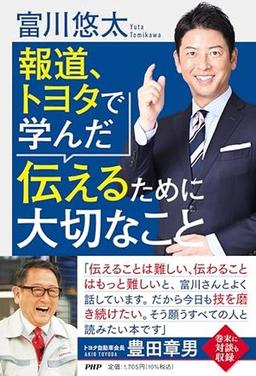相手の視点に立った聞き方・話し方
伝わる話し方と、聞き取りやすい話し方は違う
伝わる話し方とはどのようなものか。著者は、「相手の視点に立つ」ことと「第三者的視点で自分を見る」ことで、本当に伝わりやすい表現ができているかがわかるという。
ハキハキと流ちょうに話せば伝わりやすいと思うかもしれない。だが、「聞き取りやすい」と「伝わりやすい」は違う。聞き取りやすい話し方に意識を向けすぎると、かえって聞き手の印象に残りにくいこともある。それは、聞き手が自分ごととして思えず、臨場感を持てないからだろう。
大事なのは、話し方より「視点」を意識することだ。まず、取材の際など「現場と一体化する」とき、自分の視点は現場の視点になる。現場で起きた事件、災害などの当事者に近い視点で物事を見る。つづいて、視聴者の視点になり、視聴者が「知りたいこと」をもとに伝え方を考える。そのうえで、実際に伝える際には、現場と自分と視聴者とを含めた全体を見る視点に立ってみる。現場中継なら、現場で自分が話す様子を離れた場所から見るようなイメージだ。
話し手が話の内容に入り込むと、現場のニュースが話し手にとっての自分ごとになる。そのため、説得力のある「自分の言葉」で話せるようになり、結果的に相手に伝わりやすくなるのだ。
「上がり込みの達人」といわれるまでに

人気報道番組のリポーターになった著者は、事件や事故の現場に行って取材をすることになった。当初は土足で上がり込むような気がして、インタビューをするのは気が重かったという。
それが変化したのは、2004年の新潟県中越地震のときだ。現地へ赴いた著者の前には惨状が広がっていた。建物は倒壊し、土砂崩れも起きて、家に帰れない人がたくさんいる。著者は、取材よりもお手伝いが先だと思い、瓦礫の片づけを手伝った。すると、一緒に作業をしている現地の人が、自然と話してくれた。相手の立場に立って役に立つことを探し、一緒に作業する中で自然に出てくるものを拾う。こうした取材の仕方のほうが、質問して答えてもらおうとするより、はるかにリアルな話を聞けたのだ。