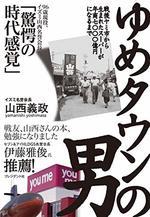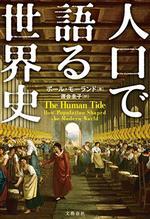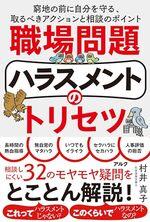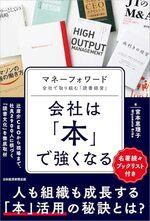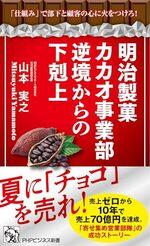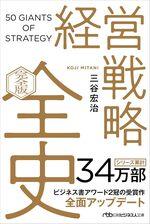心理学的経営の考え方
ありのままの人間に対する理解

タテマエに対するホンネ、合理的なシステムに対する非合理的な人間の行動、そして表のマネジメントに対する裏のマネジメント。こうした対比のなかで、ありのままの人間への理解を中心に据えた企業経営とは何か。このテーマについて思索を深めていくのが、心理学的経営の基本的なスタンスである。
官僚組織などは、ムダを省いて最も効率的なシステムを志向する。こうした組織は、指示系統を単一にすることで、情報からできる限り余計なノイズを取り除こうとする。しかし、そもそも人間の行動というのは、このノイズとしてのムダな情緒や感情を基底に持つところに、その本質がある。人間は様々な欲望を抱え、感情の狭間で揺れ動く。心理学的経営においては、人間の現実をありのままに受け入れることを何よりも重視する。そのうえで、「感情」こそ人間の行動に重大な影響を及ぼす要因だと考えるのだ。
人間を合理的存在としてだけ見ようとすれば、必ず合理的な尺度におさまりきらない、ある種の不純物が吹き出してくる。企業組織にはルールがあるが、現実に人々が従っているのは、行動を規制するルールではない。暗黙のうちにつくられた互いの合意であり、そこから生まれた規範だ。どろどろとした現実を直視するところに、心理学的経営の重要な視点がある。企業における働く人々の自己実現、豊かな人生の実現。両者が心理学的経営のゴールであり、同時に一筋縄では解決に至らない究極のテーマでもある。
【必読ポイント!】 働く意欲を生み出すもの
モティベーションの要因

旧来の経営組織論では、組織のなかで働く人は、働くことを忌避するものという前提で、制度や規則がつくられてきた。しかし、現代の労働者に関しては、最低限の生活の保障を得るという欲求が充足されているかどうかだけを見ていてはいけない。彼らが仕事を好み、自ら挑戦していく側面を持っていることも考慮しなければならない。
心理学者フレデリック・ハーズバーグは、アメリカのホワイトカラーを対象に、職務満足に関する研究を行った。この研究によると、職務満足をもたらす要因は、仕事に関連する要因のみであった。たとえば、仕事で何かを成し遂げる達成感を経験したとき、上司や仲間から仕事を認められたとき、責任の重い仕事を任されたとき、仕事を通して自分の成長を実感できたときなどだ。
一方で、職務不満足をもたらすのは仕事そのものよりも作業条件、給与、会社の制度、上司の監督技術など、仕事の環境要因であるという。これらの要因が満たされても、積極的に満足をもたらす力にはなりえない。しかし、充足されないときには不満足感をもたらすことが明らかになった。
つまり、人びとを仕事に対して強くモティベートさせる要因は、給料や条件面ではなく、仕事そのものや仕事の過程といった、人間的要素に深く関わっている。さらには、達成感や成長感、承認欲求の充足につながっているのである。
また、目標がはっきり意識されることも行動への動機づけとなる。行動科学の実験結果によると、「とにかくがんばれ」では、目標としての動機づけになりにくい。「背伸びをすれば届きそうな程度の難しい目標」が提示されることで、より大きな効果を生み出すことがわかった。日本の経営者には、不可能と思える目標を提示する例が見受けられる。これでは、働く人たちの拒絶反応を招いたり、やる気を削いだりするかもしれない。
ただし、松下幸之助のように、あえてとんでもない目標を従業員に投げかけることで、創造的破壊が生じるケースもある。新商品の誕生や新しい市場の創出、抜本的なコストダウンなどは、現状の延長では生まれにくい。
集団目標のもたらす効果
日本的経営の特徴として「集団主義」が指摘される。ある研究によると、単独で個人に目標が与えられた場合よりも、集団で目標が設定された場合の方が、業績を高める効果が大きいことがわかった。集団目標が設定されることで、メンバーたちは責任を共有する。さらには、集団目標と個人目標のそれぞれに対してフィードバックがなされることで、相乗効果が生まれるのだ。
生産性を決定づける心理
ホーソン実験と呼ばれる有名な研究がある。これによって見出されたいくつかの心理的事実は、当時、経営者の人間観を変えるほど衝撃的なものだった。