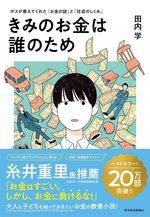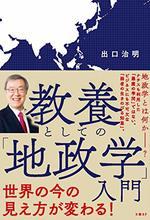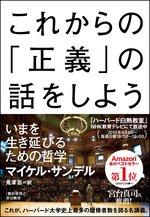【必読ポイント!】 数値と客観性の信仰が生む息苦しさ
「先生の言っていることに客観的な妥当性はあるのですか」

著者は、医療現場や貧困地区の子育て支援の現場で行ったインタビューを題材に、大学1、2年生の授業を担当することがある。そうしたとき、「先生の言っていることに客観的な妥当性はあるのですか」という質問を受ける。著者の研究は、対象者の語りを丹念に分析するものであり、数値による裏付けはない。そういう意味で、学生が客観性に欠けると感じるのは自然なことだ。
一方で、「客観性」や「数値的なエビデンス」を絶対の真理と見なすことに対する違和感も拭えない。客観的なデータでなかったとしても、意味がある事象は存在する。客観性だけに価値をおく社会では、一人ひとりの経験が顧みられなくなるのではないか——。
「誰でも幸せになる権利があると言うが、障害者は不幸だと思う」
「働く意思がない人を税金で救済するのはおかしい」
授業のなかで、こんな声が聞かれたこともある。学生たちの意見は、社会の代表的な意見であるだろう。社会的に弱い立場に置かれた人に対して、学生たちが冷淡なのは、そもそも社会にそうした人たちへの厳しい目があるからだ。
社会的に弱い立場の人に厳しくあたる傾向は、客観性を重視する傾向と無関係ではない。両者は、数字に支配された世界で人間が序列化されているという点で共通している。常に競争の恐怖に怯える序列化された世界で、幸せになれる人はほとんどいない。学生たちが社会へ向けた厳しい目線は、翻って自分たちを数字による競争に縛り付け、苦しめることになっている。
本書は、私たち自身を苦しめる発想の原因を、数値と客観性の過度な信仰のなかに探っていく。
客観性が真理となった時代
客観性の誕生
世界のあらゆる事象が客観的にとらえられるものになっていったのは、19世紀から20世紀にかけてのことである。客観性を重視する世界の歴史は、まだわずか200年弱しかない。