余裕のあるアタマをつくる
頭のなかを空地にする
勉強すると、頭は悪くなる。知れば知るほど、バカになる。
いくら頭のなかにゴミをつめこんでも、賢くなるわけがない。頭をよくしたければ、頭のなかに入っているよぶんなものを捨ててしまうことだ。
情報は、たちまち忘却のなかへ棄(す)てさってしまおう。去るものは追わずに忘れてしまうこと。そういう人間の頭は、いつも白紙のようにきれいだ。頭の中が空地だから、新しいものを建てられる。
不要な知識は捨てる
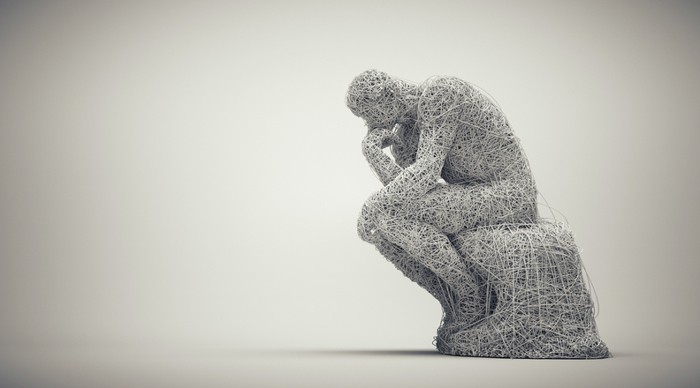
思考には二種類ある。すなわち、目的思考と自由思考だ。
明確な対象を持って考える場合、それを目的思考という。それに対して、課題や問題にしばられることなく、まったく頭を自由に働かせるのが自由思考だ。発明や発見をもたらすのは、自由思考のほうである。
子供の発想は、しばしば天才的だ。それは、子どもの頭が知識でいっぱいになっていないからだろう。頭のなかがあいているから、自由思考に適しているのだ。
子供の例をみればわかるように、知識をふやしすぎると、自由思考を邪魔してしまうことがある。知識があふれれば、それはもはやゴミ同然だ。不要な知識は捨ててしまわなければならない。
わからないことは放っておけ
わからないことこそ心に残る
謎と疑問をそのままにしておくと、ある日偶然、その答えを悟ることがある。読書においても、本当に影響を受けたと言えるものは、たいていはじめはよくわからなかった本だ。わからないからこそ、いつまでも心に残って忘れない。反芻するからこそ、やがて心の深いところに到達するのだ。
すぐにわかることは、得てしてすぐ忘れてしまう。一方、ぱっとわからないことは、あれこれ時間をかけて考えたり、文章を何度も読み返したりする。そのうちに時間が味方して、未知の対象とわかろうとする人間が少しずつ変化し、通じ合うようになるのだろう。
知識は時間をかけて深まっていく
知識というのは、常に変化しながら流れているものだ。上辺だけを流れている流水は、ただの流行であって、いずれほとんどが消えてしまう。
そういった流れのうち、ごく一部が地面にもぐり、長い時間をかけて地下に到達する。そして水脈となり、やがて泉となって湧き出してくるのである。そのときになれば、知はすっかり形を変えている。
未知の読みと既知の読みの違い
新しいことを知るのは大変だ。手がかりになるものがないため、まずわからないと覚悟したほうがよい。




















