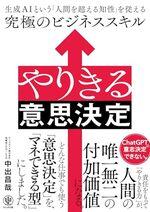なぜ行動できないのか
脳はリスクに備えている

最近の社会変化のスピードは、人間の脳がついていけるレベルを超えている。
フロリダ州立大学のボーマイスターの研究によると、人は急な社会変化に直面すると「決断疲れ」に陥りやすくなる。選択をしなければいけない場面が頻繁に起こることで、判断能力が鈍り、大事な行動を避けるようになるのだ。
それに加え、人は未来を予測できないと、動くことを本能的に避け、様子を見ようとする傾向がある。進化心理学的な観点から考えると、人間の脳は旧石器時代からほとんど変わっておらず、当時の危険に満ちた環境に適応したまま生きている。つまり、人間の脳は常に最悪のケースに備えて行動するように設計されているのだ。
新しいことを始めるときに不安を感じるのは、脳がリスクに反応していることが原因である。変化をせずに今のままでいれば、リスクを負うことはないと脳が判断しているのだ。
「ネガティビティ・バイアス」といって、人間は危険を避けるために、ネガティブな情報に注目する傾向がある。もちろんリスクを避けるために慎重になることは大切だ。しかし、過剰なほど慎重になるとチャンスを逃してしまう。
行動して失敗するリスクに対し、行動しなかったことで得られなかったものは、認識しづらい。提案していたら通ったかもしれない企画や新たなスキルを得られたかもしれない誘いなど、行動しなかったことで何かを失っているかもしれない。そう考えると、行動しないことにもリスクがあるといえる。
そんな心理的なリスクと致命的なリスクを区別し、見極めることが重要だ。
「やらない後悔」は後を引く
やったほうがいいとは思うものの、先延ばしにしてしまった経験がある人は多いだろう。
変化はエネルギーや不確実性を伴う。その懸念から、人間の脳には現状維持しようとする「現状維持バイアス」がある。人には本能的にできるだけ少ない負荷とエネルギーで行動をしようとする「最小努力の原理」と呼ばれる傾向もある。人がいつも通りの行動をしようとするのは、こうした働きによるものだ。