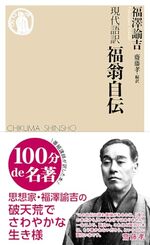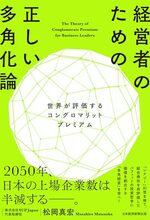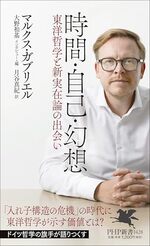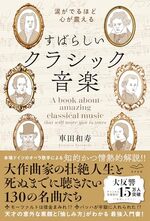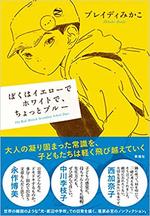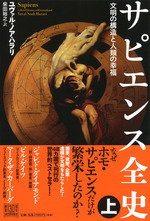教養主義とは
教養主義という文化
『世界』や『中央公論』といった総合雑誌の購読によって教養主義者となり、教養共同体を形成する。文学、歴史、哲学などの本をたしなみ、「あれもこれも」の「大正教養主義的な様式をなぞった読書生活」。そうした一部のプチ教養主義者が、「ニーチェのいう教養俗物のようなものであったことは否めない」。サルトルブームにしても、学生の多くは作品の中身を理解していなかっただろう。「教養知は友人に差をつけるファッションだった」。教養崇拝は、学歴エリートという「成り上がり」の者たちが「教養」によって「『インテリ』や『知識人』という身分文化を獲得する手段」でもあった。こうした不純な動機は、キャンパスの規範文化に覆い隠され、意識されることはなかった。だが、動機が不純と言えど、教養によって人格を完成させ、知識によって社会をよりよい方向に導きたいと考えたこともまた、嘘ではない。こうした教養主義はどうして学生を魅了したのだろうか。そして、なぜ教養主義からそうした魅力が喪失したのだろうか。本書の対象は教養そのものではなく教養主義、ひいては「教養主義者の有為転変のほうにある」。近代日本社会の歩んできた道を踏まえつつ、教養主義と教養主義者の軌跡から、エリート学生文化のうつりゆく風景を描き出すのが本書の目的である。
旧制高校という場所

1932年生まれの戦後作家、黒井千次と石原慎太郎は、旧制中学校に入学しながら、戦後の学制改革により新制高等学校を卒業、新制大学に入学した世代だ。2人よりも3歳若い大江健三郎を「純」新制高校世代とすると、黒井も石原も「半」新制高校世代といえるだろう。その意味において、「旧制高等学校世代ともっとも接近した新制高校世代」なのである。それゆえ彼らは、「旧制高校的なるものや旧制高校的教養主義に対するなんらかのスタンスをとらざるを得なかった」のであり、しかも、黒井は継承・反復、石原は反撥・侮蔑という正反対の態度であった。