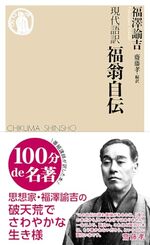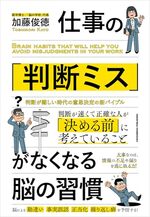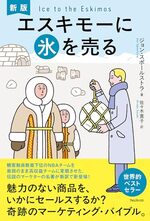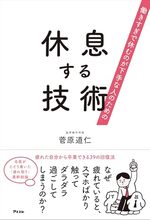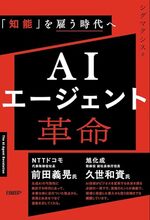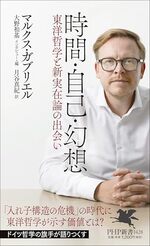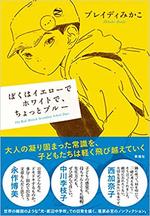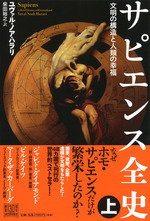【必読ポイント!】 心の声を表現した、「音楽の父」バッハ
小さなオルガンに導かれ
著者は大学4年生のとき、ドイツ東部のザクセン州にあるラインハルツグリンマという村を訪ねたことがある。バッハが生きていた時代のオルガン製作者ゴットフリート・ジルバーマンの作ったパイプオルガンを一目見たかったのだ。交通の便が悪い小さな町の教会にたどり着くと、鍵がかかっていて自由には入れないようになっていた。牧師の家を教えてもらい、この教会のオルガンを見るためにはるばる日本からやってきたことを伝えると、教会の鍵を貸してもらうことができた。ジルバーマンのオルガンは小さいけれど美しく、教会の中で、圧倒的存在感を放っていた。こんな小さなドイツの村まで著者を導いたのは、バッハの存在だった。バッハの足跡を自分の目で見てみたいという気持ちに導かれ、のちにはドイツ留学をするまでになる。それから今も音楽をやっているのは、バッハをはじめとした多くの作曲家に導かれたからに他ならない。
バッハの生涯

1685年、ドイツ中部、アイゼナハで音楽一家に生まれたヨハン・セバスチャン・バッハは、音楽と同時に神学の教育を受けて育った。アイゼナハは宗教家ルターが青年時代を過ごした街でもあり、バッハと宗教との結びつきは強かったといえる。幼い頃に両親を亡くしたバッハは兄に育てられ、22歳でマリア・バルバラと結婚し、7人の子供をもうけた。しかし、30代でマリア・バルバラは亡くなってしまう。2番目の妻となるアンナ・マグダレーナとは13人の子どもをもうけたが、合わせて20人生まれた子どものうち、10人を亡くしている。身近な人の死を多く経験したバッハは、悲しみのなかで神に救いを求めたのかもしれない。バッハは多くの宗教音楽を作り、悲しみや救い、癒しや祈りが音楽の大きなテーマだった。「音楽の父」と呼ばれるバッハの音楽を聴くときには「バッハにとって神とはどのような存在だったのか」を無視することはできない。様々な宗教的な題材が取り上げられているが、そこで描かれているのはバッハが題材に触れて動いた「心」だ。バッハの音楽からは人の「心の声」が聞こえてくる。